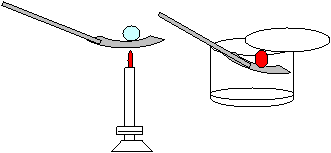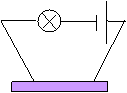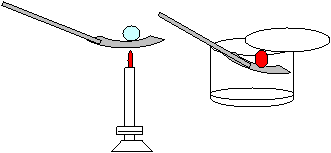| K5111 |
物質を加熱したときの変化を調べよう |
|
|
百科事典へ |
※ 観察のポイント |
・砂糖の変化を順を追って観察させる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・やけどに注意(石灰水の変化は、教師の演示実験とした) |
|
|
テーマ |
白い粉を加熱したときの変化を調べる |
|
|
準備物 |
砂糖、食塩、小麦粉(デンプン)、重そう、スプーン、加熱器具 |
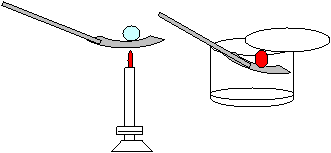
|
|
|
実験 |
1 加熱したときのようすを観察する |
|
砂糖など |
|
火のついた砂糖など |
|
|
|
砂糖 、 食塩 、 小麦粉を少量アルミ箔をまいたスプーンに取り |
|
|
|
|
|
ガスバーナーの上で加熱する。 |
|
|
|
2 1で火のついた物質について、石灰水の変化を調べる。 |
|
|
|
1で、火がついたら、臭気ビンに入れ、火が消えたらスプーンを取り出す。 |
|
|
|
この中に、石灰水を入れ、よく振り、変化を調べる。 |
|
石灰水 |
|
|
結果 |
|
|
物質名 |
砂糖 |
食塩 |
小麦粉 |
重そう |
|
物質名 |
砂糖 |
食塩 |
小麦粉 |
重そう |
|
|
加熱する |
|
|
|
|
|
加熱する |
溶け、黒くなり、燃える |
変化なし |
黒くなり、燃える |
変化なし |
|
|
石灰水を入れよく振る |
白くにごる |
**** |
白くにごる |
**** |
|
石灰水を入れよく振る |
白くにごる |
**** |
白くにごる |
**** |
|
|
|
問い |
|
省略 |
|
|
(1) |
この実験をしようとする場合、準備物に不足のものがあった。 |
|
|
|
|
|
|
不足している薬品または器具を2つ答えなさい。(但し、マッチなど加熱器具関係は除く) |
|
上記 |
|
|
(2) |
砂糖、食塩、小麦粉を加熱したときのようすを答えなさい。 |
|
|
|
|
(3) |
砂糖、小麦粉は、有機物と呼ばれる。 |
|
黒くなり、燃え、二酸化炭素を発生する |
|
|
|
この実験から砂糖や小麦粉に共通する点を書きなさい。 |
|
|
|
|
(4) |
有機物に対して、食塩などは、何と呼ばれるか、答えなさい。 |
|
無機物 |
|
|
物質と原料、精製方法 |
|
|
有機物と無機物 |
物質 |
|
砂糖 : |
サトウキビを搾り、漂白、乾燥したものです。 |
|
|
有機物 : |
砂糖や小麦粉のように、加熱すると黒くこげたり、二酸化炭素を発生したりする物質をいう。 |
|
食塩 : |
海水から水を除く。または、岩塩です。 |
|
|
無機物 : |
有機物以外の物質をいう。 |
|
重曹 : |
成分は、炭酸水素ナトリウムです。 |
|
|
|
|
|
|
資料 : |
有機物と無機物 |
|
|
|
k5112 |
|
| K5112 |
金属の性質を調べよう |
|
百科事典へ |
※ 観察のポイント |
・金属全てが磁石に着くと思っている生徒がいる。 |
|
|
|
|
テーマ |
身近な物質が金属かどうか調べる |
|
|
|
磁石に着くか |
|
|
|
準備物 |
|
|
|
方法 |
1 いろいろな物質について、電流が流れるかどうか調べる |
|
|
N極 |
|
|
くぎ、アルミニウム、つりのおもり、クリップ、ガラス片、シャープ芯、銅線 |
|
|
|
|
S極 |
|
|
2 電流が流れるものについて、次のことを調べる |
|
|
|
① みがいてみる |
|
|
いろいろな物質 |
|
|
② たたいてみる |
|
|
|
③ 磁石につくかどうか |
|
|
|
実験結果 |
|
|
|
鉄 (釘 くぎ ) |
アルミニウム |
おもり(鉛) |
クリップ |
ガラス片 |
シャープ芯 |
銅線 |
|
|
|
釘(クギ) |
アルミニウム |
つりのおもり |
クリップ |
ガラス片 |
シャープ芯 |
銅線 |
|
電流が流れるか |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
電流が流れるか |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
|
磨(みが)く |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
磨(みが)く |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
たたく |
|
|
伸、展 |
|
|
|
|
|
たたく |
伸、展 |
伸、展 |
伸、展 |
伸、展 |
壊 |
壊 |
伸、展 |
|
磁石につくか |
|
|
× |
|
|
|
|
|
磁石につくか |
○ |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
|
問い |
|
|
|
|
(1) |
電流が流れるかを調べるには、何が必要ですか。電流を調べる |
|
|
|
|
|
に必要な器具、道具を2つ以上書きなさい。 |
|
電池、電球、など |
|
|
|
(2) |
実験結果の表で、電流が流れる物質に○印をつけなさい。 |
|
上記 |
|
|
|
(3) |
磨いて、変化のないものに(×)印、輝くものに(○)印をつけなさい。 |
|
上記 |
|
|
|
(4) |
たたいて、伸びるものに(伸)、広がるものに(展)、割れるものに(壊) |
|
|
|
|
|
を書きなさい。 |
|
|
上記 |
|
|
|
(5) |
磁石につくものに(○)印、つかないものに(×)印をつけなさい。 |
|
上記 |
|
|
|
(6) |
この実験から、金属に共通する性質を3つ答えなさい。 |
|
電流が流れる、展性・延性がある、金属光沢 |
|
|
|
|
|
金属の特徴 |
|
|
|
金属には電流が流れる。(金属の伝導 でんどう) |
※ 伝導: 電気や熱が伝わること |
|
|
|
金属を磨くと光る。(金属光沢 きんぞくこうたく) |
|
|
|
金属は延びる。(金属の延性 えんせい) |
|
|
|
|
金属は叩くと広がる。(金属の展性 てんせい) |
|
|
|
金属は熱を伝える。(金属の伝導 でんどう) |
|
|
|
|
※ 磁石に付くのは鉄のみ |
|
|
|
|
E0001 |
|
| E0001 |
物質の密度を比べよう |
密度を求める(VBA利用) |
|
百科事典へ |
|
※ 実験のポイント |
・メスシリンダー、電子てんびんの扱いを学習してから実験をする |
|
|
|
|
|
・未知な物質を用意して、学習後、判定させるのもよい |
|
|
テーマ |
物質の密度を調べ、固体名を言おう |
|
|
|
準備物 |
物質 A 、 B 、 C 、 D 、メスシリンダー、電子てんびん |
|
|

|
|
|
方法 |
|
|
|
|
1 物質 A B C D の体積をはかる。 |
|
|
物質をメスシリンダーに入れ |
|
|
|
物質 A 、 B 、 C 、 D |
|
|
物質の密度 g/cm3 (固体) |
|
体積の変化で体積を測定 |
|
|
|
2 物質 A B C D の質量をはかる。 |
|
|
亜鉛 |
7.12 |
|
|
|
物質 A 、 B 、 C 、 D |
|
|
アルミニウム |
2.69 |
|
|
|
|
金 |
19.3 |
|
|
結果 |
|
銀 |
10.5 |
|
鉛 |
アルミニウム |
鉄 |
金 |
|
|
物質名 |
A |
B |
C |
D |
|
鉄 |
7.86 |
|
物質名 |
A |
B |
C |
D |
|
|
質量 g |
83.4 |
55.5 |
79 |
162.1 |
|
銅 |
8.93 |
|
質量 g |
83.4 |
55.5 |
79 |
162.1 |
|
|
体積cm3 |
7.4 |
20.6 |
10.1 |
8.4 |
|
鉛 |
11.34 |
|
体積cm3 |
7.4 |
20.6 |
10.1 |
8.4 |
|
|
密度(g/cm3) |
11.3 |
|
|
|
|
ニッケル |
8.85 |
|
密度(g/cm3) |
11.3 |
2.694175 |
7.821782 |
19.29762 |
|
|
マグネシウム |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
物質 A の密度は、11.3 である。では、物質、B 、 C 、 D の密度はいくらか。密度を答えなさい。 |
|
|
上記 |
|
|
(2) |
物質 A は、鉛である。物質、B 、 C 、 D の物質名をそれぞれ答えなさい。 |
|
|
上記 |
|
|
(3) |
体積は、メスシリンダーに水を入れ、その水の中に物質を入れた後の体積の変化で |
|
|
|
|
|
|
物質の体積を測定した。 |
|
|
|
|
|
|
メスシリンダーの目盛りを読むときの注意を下記の点について、それぞれ答えなさい。 |
|
|
|
|
|
|
① メスシリンダーの目盛りを読むときの目の高さについての注意点を答えなさい。 |
|
|
目は目盛りと水平の位置 |
|
|
|
② メスシリンダーの目盛りを読むときの目盛と目分量の関係について、答えなさい。 |
|
|
最小目盛りの1/10まで、目分量で読む |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|