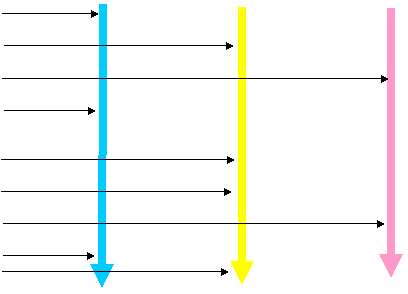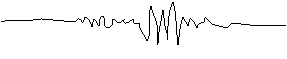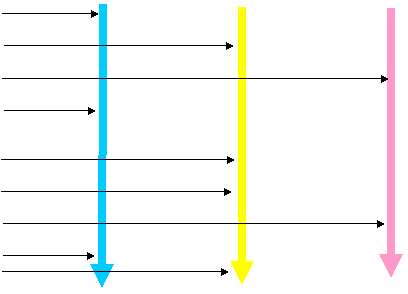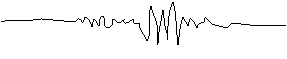|
|
�� |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�������� |
���Z�L�c�C���� |
�ߑ����� |
|
������ |
|
���މ� |
|
�s���S�ϑԂ̍��� |
|
|
�@ |
|
���މȁ@�F |
���炾�͑������̂������A���͗��𐅂ɎY�ݗ��Ƃ��B�Î~����Ƃ������𐅕��ɂ���B�x�ނƂ��́A���𐅕���艺����B |
|
|
�@ |
|
���� |
�S�@�`�@�P�O�@�� |
|
|
�@ |
|
���i���j�F |
���n����ƁA�̂��A���ΐF�ɂȂ�B |
|
|
�@ |
|
�Y�i���j�F |
���n����ƁA�����̖̂��[�������Ȃ�B���́A�D���F�B |
|
|
�@ |
|
���z |
�e�n�̕��n�ɐ��� |
�c���́A���c�A�����܂�Ȃǐ���ɂ���B |
|
|
�@ |
|
picture(�������ށj |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
COD |
���w�I�_�f�v���ʁiChemical Oxygen
Demand) |
|
|
�@ |
|
�����̔�_�����A���ɗL�@�����_���܂ɂ���ď��������ۂɏ����_�f�ʂ�mg/���ŕ\�������� |
|
|
�@ |
|
���̒l�������قǗL�@���ɂ�鉘�����i��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B |
|
|
�@ |
|
BOD�i�������w�I�_�f�v���ʁj���͐�̉���̎w�W�ƂȂ邱�Ƃɑ��āACOD�͌Ώ��y�ъC��̉��� |
|
|
�@ |
|
�̎w�W�ɂȂ��Ă��܂��B |
|
|
�@ |
|
�o�_���� |
�L�@�� |
�_���� |
���� |
�w�W�@�p |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
����̂䂪���o |
�傫�Ȏ��ʂ̎��͂ł́A����i���ԂƋ�ԁj���Ȃ���B |
|
|
�@ |
�i��ʑ��ΐ����_�j |
�i�P�X�P�X�N�@�F�����H�ŁA���z�̉��Ɍ����鉓���̐����A���z�߂��ɂȂ��ꍇ�ɔ�ׁA��������Ċϑ����ꂽ�B�j |
|
|
�@ |
�����V���iH16.5.9�j |
���o�q���u�O���r�e�B�E�v���[�O�@GP-B�v��ł��グ���B�i�Q�O�O�S�N�S���@NASA�j |
|
|
�@ |
|
����̋Ȃ���̑��A�Ђ�������ʂ̌��o���ړI�Ƃ��Ă���B |
|
|
�@ |
|
�Ђ�������ʁF��ʑ��ΐ����_�ɂ́A��]�̉e��������B�n���̎��]�����ɃW���C���̉�]��������������͂��ŁA |
|
|
�@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������o����ړI |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�������� |
�n�w���͐ς����N����������A�L�����z���āA����Z���Ԃɉh���Đ�ł����������p������B |
|
|
�@ |
|
���̂悤�ȉ����������Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�@�T�����E�`���E�̉��A�t�Y���i�̉��A�E�~�����̉��A�����{�N�̉���������ꍇ�B |
|
|
�@ |
|
���̂悤�ȉ���������N����Ð���Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�@�A�����i�C�g�̉��A�m�C�Z�����X�̉��i�L�j�A�C�O�A�m�h���ނ�������ꍇ |
|
|
�@ |
|
���̂悤�ȉ���������N��𒆐���Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�@�i�E�}���]�E�̉��A�f�X���X�`���X�̉���������ꍇ |
|
|
�@ |
|
���̂悤�ȉ���������N���V����Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���̐��� |
���̂܂��̋�Ԃɂ́A�S���Ȃǂ���������͂��͂��炭�B |
|
|
�@ |
|
�S���͎�����͂���B���̗͂����͂Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
�܂��A���͂̂͂��炢�Ă����Ԃ����E�Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
����ɁA���E�̌����i���ʌv��N�ɂ��w�������j���Ȃ����������͐��Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
�o�@�d���@�p |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���w���� |
�@�n�w���͐ς��������̊����悭�������B���ݐ����Ă��铯�����Ԃ̐����̐��������瓖�� |
|
|
�@ |
|
�̊��𐄒肷��B���̂悤�ȉ������w���Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�@�T���S�̉���������ƁA�����������ĐC���������B |
|
|
�@ |
|
�@�V�W�~�̉���������ƁA�W���ƊC�����܂���͌��ł������B |
|
|
�@ |
|
�@�z�^�e�K�C�̉���������ƁA�₽���C�̉����ł������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���ʕۑ��̖@�� |
���w�����̑O��ł́A�����S�̂̎��ʂ͕ς��Ȃ��B |
|
|
�@ |
|
������ꂽ�n�������F�y�b�g�{�g���������Y�_���f�i�g���E���i�����j�����������������_������A���]�����������́A�����O�E���������������Ȃ��B |
|
�Y�_���f�i�g���E�� + |
���_�@�@�� |
��_���Y�f�@�@�@�{�@�@�@���@�@�@�@�{�@�@�����i�g���E���@�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
NaHCO3 |
+ |
�g�b���@�@�� |
�b�n2�@�@�@�@�@�@�@�{�@�@�@�@�g2�n�@�@�@�@�{�@�@�@�m���b�� |
|
|
�@ |
���{�A�W�F |
���e�풆�ł̔��� |
|
|
�@��_���Y�f�̔������锽�� |
|
|
�@ |
|
�@���e�풆 |
�@ |
�A���e�풆 |
�����O�S�� |
������S�� |
�J��S�� |
|
|
�@ |
|
�ʼn��_���삵 |
���_ |
�œS��R�₷ |
57.28g |
57.27�� |
56.62g |
|
|
�@ |
|
���w������ |
�@ |
|
|
|
�@ |
|
���� |
�ΊD�� |
|
�A�S�Ǝ_�f�̔��� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�����O�S�� |
������S�� |
�J����S�� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
200.3g |
200.3g |
200.44g |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���� |
�@ |
������ |
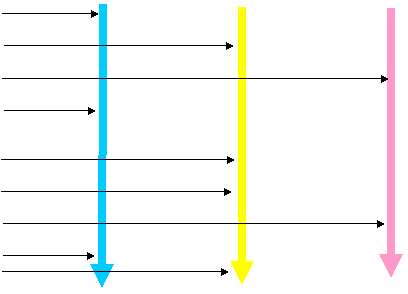
|
�Y������ |
�^���p�N�� |
���b |
|
|
�@ |
�A�~�m�_ |
�@ |
���o |
���t���� |
�A�~���[�[ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�u�h�E�� |
�@ |
�����y�f |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�u�h�E���@�@�F |
�Y�������́A�A�~���[�[�A�}���^�[�[�̏����y�f�̉e�����A���q�̏����ȃu�h�E���ɏ��������B |
|
|
�@ |
���b�_�E�O���Z���� |
�@ |
�� |
�݉t���� |
�@ |
�@ |
�y�v�V�� |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�����y�f |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�A�~�m�_�@�@�@�F |
�^���p�N���́A�݉t���̃y�v�V���̓����ɂ��A���q�̏����ȃA�~�m�_�ɏ�������Ă����B�i�y�v�V���͋����_���̉t�̒��ł͂��炭�j |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�_�` |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�_�`�_�� |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���b�_�E |
|
|
�@ |
|
�@ |
�\��w�� |
�@ |
�A�~���[�[ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
�@�O���Z�����@�F |
���b�́A�_�`�_���A���p�[�[�̉e�������b�_�ƃO���Z�����ɂ܂ŏ��������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
�����t���� |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�����y�f |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�g���v�V�� |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�v�`�^�[�[ |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
���p�[�[ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
���� |
�����̕ǂ� |
�}���^�[�[ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�����y�f |
|
�@ |
�v�`�^�[�[ |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�ŏI���� |
�u�h�E�� |
�A�~�m�_ |
���b�_�E�O���Z���� |
|
|
�@ |
|
�@ |
�z���ꏊ |
�����_�сi�э��ǁj |
�����_�сi�����p�ǁj |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�����튯 |
�H������K�v�ȗ{�������炾�̒��Ɏ������͂��炫�����Ă���튯�������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
������ |
�H���̒ʂ蓹�͌�����n�܂�C�H���C�݁C�����C�咰��ʂ������ɏI���P�{�̒����ǂł���B���̊ǂ������ǂƂ����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�����y�f |
�傫�ȕ��q�������ȕ��q�ɕ�������͂��炫�̂��镨���������B |
(��̕\���Q�l�ɂ���Ƃ悢�B) |
|
|
�@ |
|
���t���̃A�~���[�[�́C�Y�������ɓ����C���q�̑傫���Y�������q�̏����Ȕ��蓜�ɕς���B�@�����y�f�́C�A�~���[�[�ł��B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�����ǂʼn��M |
�����ǂɓ����t�ʂ́A1/4�@����@1/5�@�ɂ���B�����i�f�Ă��̔j�ЁA���́A���̊J�����K���X�j������B |
|
|
�@ |
|
�����ǂ������݂ɐU��Ȃ�����M����B�t�R���A�ˑR�̕����ɒ��ӂ���B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���R�Ȋw |
���̂����炻���Ȃ��Ă�����̂������A���̖@���������o���B |
|
|
�@ |
|
{ �V�� |
�n�� |
���� |
���� |
���w |
|
�d�C |
�C�ہ@�p |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�V�}�~�~�Y |
���Z�L�c�C���� |
�`�����i�����ǂ��Ԃj |
�n�їށi�Ђ�����邢�j |
|
|
�@ |
|
�̒� |
�P�O�O���� |
|
|
�@ |
|
���� |
�����t�₭�������A���Ȃǂ�H�ׂ鏬�����̂ЂƂB |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�������\ |
���q�����ʂ̑傫���Ɛ��������Ƃɕ��ׂ��\�������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�L�f |
���q�ԍ��@�R�T�@�A���q�ʁ@�W�O |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�W���Y�_�} |
��q�A���@�@��q�A���@�@�P�q�t�A���@�@�@�C�l�ȁ@�@�W���X�_�} |
|
|
�@ |
|
����@�@�@���N�� |
|
|
�@ |
|
�w��@�@�P�@�`�@�P�D�T�@���@ |
|
|
�@ |
|
����ꏊ�@�@�@�����A���� |
|
|
�@ |
|
�J�Ԏ����@�@�@�W�@�`�@�X�@�� |
|
|
�@ |
|
�����@�@�@�ʎ��́A�W���Y�ʂɎg���@�@ |
|
|
�@ |
|
picture(�W���Y�_�}�j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�V���� |
��q�A���@�@��q�A���@�@�P�q�t�A���@�@�@���V�ȁ@�V���� |
|
|
�@ |
|
����@�@�@��Ύ� |
|
|
�@ |
|
�w��@�@�R�@�`�@�T�@���@ |
|
|
�@ |
|
����ꏊ�@�@�@�сi�͔|�j |
|
|
�@ |
|
�J�Ԏ����@�@�@�X�@�`�@�P�P�@�� |
|
|
�@ |
|
�����@�@�@���Y�ي��i���䂤������j�@�@ |
|
|
�@ |
|
picture(�V�����j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�H���A�� |
���R�E�̒��ŁA�����ǂ����́A�u�H�ׂ�E�H�ׂ���v�Ƃ����H���A���̊W�łȂ����Ă���B |
|
|
�@ |
|
���c�Βn�̐H���A�� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�g�r |
|
���H�̒��� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�w�r�i�}���V�A�A�I�_�C�V���E�A���}�J�K�V�j |
|
���H���� |
|
|
�@ |
|
�@ |
�J�G���i�g�m�T�}�K�G���j�A�l�Y�~�i�A�J�l�Y�~�j�A���X�A���O���A�g�J�Q |
|
���H�A���H�A�G�H�̓��� |
|
|
�@ |
|
�����ށi�g���{�A�o�b�^�A�`���E�j�A�N���ށA�����ށA�`�����i�~�~�Y�j |
|
���H�A���H�A�G�H�̓����A�A�� |
|
|
�@ |
|
�^���|�|�A�V���c���N�T�A�J���X�m�G���h�E�A�����Q�A�m�Q�V�A�w�r�C�`�S�A�J�^�o�~�A�����T�L�T�M�S�P�A |
�A�� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�W�����E�O�� |
���Z�L�c�C���� |
�ߑ����� |
|
�N���� |
|
|
�@ |
|
���� |
�������ɂS�i�W�{�j |
|
|
�@ |
|
�͂� |
�Ȃ� |
|
|
�@ |
|
�G�p |
�Ȃ� |
�G��������i���ŐG��Ē��ׂ�j |
|
|
�@ |
|
�� |
�P�Ⴊ�S�i�W�j�A�������ɂ��� |
|
|
�@ |
|
�ċz�� |
���x�ƋC�� |
|
|
�@ |
|
�Ȃ��� |
�N���A�T�\���A�_�j |
|
|
�@ |
|
picture(�N���j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�Ɏ_ |
���F�A�h���L�A����M�������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�Ɏ_�J���E�� |
�Ζ�̌����ɂ��Ȃ�B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�Ɏ_�� |
����Ɏ_�ɗn�����ē���B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���U |
�A���̗t����́A�����C���O�ɏo�����B���̂��Ƃ��A���U�Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���U��p |
�t�̕\�ʂɗt�ɂ́A�C�E������A���̌��i�E�j����A��_���Y�f�A�_�f�A�����C���o���肷��B |
|
|
�@ |
|
�C�E�́A�t�̗����ɑ����A�Q�̍E�ӍזE�̕ω��ɂ���āA�C�E�̑傫����ω������Ă���B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�H���i�����i�g���E���j |
�H���́A�C�������č��B |
|
|
�@ |
|
�≖���H���Ƃ��ė��p�����B |
|
|
�@ |
|
�H���̉��w���́ANaCl�@�ŕ\�����B |
|
|
�@ |
|
���_�ɐ��_���i�g���E����������ƁA���a���āA�H�������ł���B |
|
|
�@ |
|
�o�@�@�C�� |
���� |
�≖ |
���w�� |
Na |
Cl |
|
|
�@ |
|
���_�@ |
���_���i�g���E�� |
���a�@�@�p |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�H���� |
�H���𐅂ɗn�������t�������B |
|
|
�@ |
|
�H�����́A�����I�H�����₤�����p�ɂ���������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�A������ |
�A���́A�Ԃ̍炭�A���ƉԂ̍炩�Ȃ��A���ɕ��ނ���邱�Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
�Ԃ̍炭�A���́A��삪�ނ��o���̂��̂���삪�q�[�ɕ�܂ꂽ���̂Ƃɕ������邱�Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
��삪�q�[�ɕ�܂ꂽ���̂́A�q�t���Q���̂��́i�o�q�t�j�ƂP���̂��́i�P�q�t�j�Ƃɕ������邱�Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
�q�t���Q���̂��̂́A�ԕق����ق̂��̂Ɨ��ق̂��̂Ƃɕ������邱�Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
�o�@��� |
�q�[�@�p |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�A���̂��炾�� |
�Ԃ̂��� |
�\�� |
�Ԃ́A�߂��ׂ𒆐S�ɂ����ׁA�ԕفA�����Ђ̏��ɂȂ��Ă��� |
|
|
�@ |
����Ƃ͂��炫 |
��q������ |
��q�܂� |
�߂��ׂ̒����ɉԕ������i�j�A�ԕ��ǂ����܂ŐL�юA���͎�q�ɁA����̎q�[�͉ʎ��ɂȂ�B |
|
|
�@ |
|
��q�A�� |
���� |
�Ԃ��炫�A��q�������đ�����A������q�A���Ƃ����B��q�A���ɂ́A��삪�q�[�ɂ܂ꂽ��q�A���Ǝq�[�̂Ȃ��A���q�A���Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�V���T�M |
�V���T�M |
�S�� |
�@ |
�n�@�@�@�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�ߐH |
�@ |
|
|
�@ |
|
�_�C�T�M |
�S���@�X�O�@�`�@�P�O�O���� |
�Ē��Ƃ��ēn�� |
�@ |
�@ |
�@ |
���ӂ̏����� |
|
|
�@ |
|
�`���E�T�M |
�S���@�U�O�@�`�@�@�V�O���� |
�Ē��Ƃ��ēn�� |
�@ |
�@ |
�@ |
���ӂ̏����� |
|
|
�@ |
|
�R�T�M |
�S���@�S�V�@�`�@�@�T�Q���� |
�Ē��Ƃ��ēn���A���ɂ͗���������̂����� |
�@ |
���ӂ̏����� |
|
|
�@ |
|
���������������i�V���T�M�j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�V���c���N�T |
��q�A���@�@��q�A���@�@�o�q�t�A���@�@���ىԗށ@�}���ȁ@�V���c���N�T(�N���[�o�[�j |
|
|
�@ |
|
����@�@�@���N���A�� |
|
|
�@ |
|
�w��@�@�T�@�`�@�P�T�@���� |
|
|
�@ |
|
����ꏊ�@�@�@�����E���E�� |
|
|
�@ |
|
���炾�̂���@�@�قӂ��^ |
|
|
�@ |
|
�J�Ԏ����@�@�@�S�@�`�@�V�� |
|
|
�@ |
|
�����@�@�q���␅�c�̔엿�Ƃ��č͔|�@�@�@ |
|
|
�@ |
|
�@�@�@�@�@�}���Ȃ̐A���́A���ɍ����ۂ��������Ă��āA��C���̒��f���z�����邽�߁A�悢�엿�ɂȂ�B |
|
|
�@ |
|
picture(���Ҹ��j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�l�H���� |
�l�̎�Ŏ��s���B�v�w�ԂŎ��s���Ȃ��ꍇ�A�l�̎�Ŏ��A�����e�̑ٓ��ɕԂ��� |
|
|
�@ |
|
�q����āA�o�Y����B |
|
|
�@ |
|
��O�҂̐��q�i�v�ȊO�̐��q�j���g�����ꍇ�A���������q������`��̕��e��T���n�߁A���ɂȂ��Ă���B�i2003.11.24) |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�S�� |
���t�𑗂�o�������S���Ƃ����B |
|
��� |
�x���� |
�哮�� |
�x�Ö� |
|
|
�@ |
�E�S�[ |
�q�g�̏ꍇ�A�Q�̐S�[�ƂQ�̐S������Ȃ�B�i�Q�S�[�Q�S���j |
|
�E�S�[ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�E�S�� |
�����@�F�@�S�����猌�t�𑗂�o�����ǁB�哮���A�x���� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
���S�[ |
|
|
�@ |
���S�[ |
�Ö��@�F�@�S���Ɍ��t���߂��Ă��錌�ǁB��Ö��A�x�Ö� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
���S�� |
�x�z�@�F�@�E�S������x�A�x�Ö����獶�S�[�܂ŁA�x�Ŏ_�f�Ɠ�_���Y�f�̌��� |
�@ |
�E�S�� |
�@ |
�@ |
�������̕����̋ؓ������� |
|
|
�@ |
|
�̏z�@�F�@���S������S�g�A�S�g����E�S�[�܂ŁA�̑S�̂̍זE�֗{���_�f�� |
�@ |
�@ |
���S�� |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@��A�s�v�ɂȂ����A��_���Y�f�A�{�����^�ԁB |
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���� |
���t���̂��܂��܂ȕ����������o���āC���̂��ƂŁC�ĂѕK�v�ȕ������z������B |
|
|
|
�@ |
|
�u�h�E���C�A�~�m�_�C�قƂ�ǂ̐��́C�����o����C�Ăыz�������B�z������Ȃ������ꕔ�̐��́C�s�v���Ƃ�������ɔA�Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
�̊O�ɏo�����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�_�o�n |
���o�זE��������h���́A�M���ɕς����A���o�_�o��ʂ��Ĕ]�ɓ`������B�]�ł͂ǂ̂悤�Ȕ��������邩�����߂��A |
|
|
�@ |
|
���̐M�����^���_�o��ʂ��ċؓ��ɓ`���A�^�����N����B |
|
|
�@ |
|
�h�� |
|
�_�o�n |
|
���� |
|
|
�@ |
|
���o�튯 |
|
�@ |
�@ |
�@ |
|
�^���튯 |
|
|
�@ |
|
�@ |
���o�_�o |
�����_�o |
�^���_�o |
�@ |
|
|
�@ |
|
�ځE���Ȃ� |
��� |
�@ |
�] |
�@ |
���� |
�ؓ��Ȃ� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
�������� |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�����傤�_�o |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�n�k�̂����� |
�n�k�̂�� |
�n�k�K���\ |
�n�k�̋K�́i�}�O�j�`���[�h�j |
|
|
�@ |
|
���� |
�f�w |
���~ |
���N |
�n���� |
|
|
�@ |
|
�����ꏊ |
�ΎR�̕��z�Əd�Ȃ� |
�v���[�g�̋��� |
|
|
�@ |
|
���� |
�v���[�g���m�̘c�̉��� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�n�k�i�k�x�K���j |
�k�x |
�����Q�̂悤�� |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�n�k�̂�� |
|
|
�@ |
|
0 |
�l�͂��������Ȃ� |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
1 |
�����ɂ���l�̈ꕔ���A�킸���Ȃ��������� |
�@ |
|
�@�@�������� |
�n�k�̂͂��߂̏����Ȃ�� |
|
|
�@ |
|
2 |
�����̐l�̑����������A�艺�����d���Ȃǂ��킸���ɂ���B |
|
�@�@��v�� |
���������̌�ɑ����傫�Ȃ�� |
|
|
�@ |
|
3 |
�����̂قƂ�ǂ̐l�������A�I�̐H��ނ����𗧂Ă邱�Ƃ�����B |
|
|
�@ |
|
4 |
���Ȃ�̋��|��������A�����̈����u�����|��邱�Ƃ�����B |
|
�@�@�k�� |
�n�k�̔��������ꏊ |
|
|
�@ |
|
5�@�i��j |
���K���X������ė�������A�I�̐H��ނ������邱�Ƃ�����B |
|
�@�@�k�� |
�k���̐^��̒n�_ |
|
|
�@ |
|
5�@�i���j |
�d���Ƌ�⑽���̕���|��A��v�Ȑ����ǂɔ�Q����������B |
|
|
�@ |
|
6�@�i��j |
���Ȃ�̌����̑��K���X���������A�n�����R���ꂪ�N���� |
|
�@�@�o�g |
�n�k���������A�ŏ��ɓ��������g |
|
|
�@ |
|
6�@�i���j |
�����Ă��邱�Ƃ��ł����A�ϐk���̒Ⴂ���������A�|��� |
|
�@�@�r�g |
�o�g�̌�ɑ����ē`������g |
|
|
�@ |
|
7 |
�قƂ�ǂ̌��������A�L���n��œd�C�A�K�X�A�������~�܂�B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�������� |
�n�k�̂Ƃ��A�͂��߁A�J�^�J�^�Ə��������A�����ŁA���T���T�Ƒ傫������B���̂͂��߂ɃJ�^�J�^�Ƃ��鏬���Ȃ������������Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
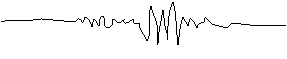
|
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�n�k�v�̋L�^ |
�@ |
|
�@ |
|
���������p������ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@�@���������̑��������Ԃ������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�������� |
��v�� |
|
�@�@���������p�����Ԃ́A�k���܂ł̋����Ɣ�Ⴗ��B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�iP�g�̑����́A��6.3�q/�b�A�r�g�̑����́A3.5km/�b�@�@���Ɍ��암�n�k�̋L�^����j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�k���܂ł̋������V�D�T�~���ԁi�b�j�@�i��X�����j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
��v�� |
�n�k�̂Ƃ��A�͂��߁A�J�^�J�^�Ə��������A�����ŁA���T���T�Ƒ傫������B���̃��T���T�Ƃ�Ă�傫�Ȃ�����v���Ƃ����B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�k���E�k�� |
�n�k�ɂ��h��́A�n���Œn�k�����������ꏊ����n�k�̔g���`����Ēn�ʂ�h���Ԃ�B���̒n�k�̔��������ꏊ��k���Ƃ����A |
|
|
�@ |
|
�k���̐^��̒n�_��k���Ƃ�ԁB |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�n�\ |
�k�� |
�@ |
�ϑ��n�_ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
�@���@�k�� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�W���m���`���E |
���Z�L�c�C���� |
�ߑ����� |
������ |
���S�ϑ������� |
�`���E�E�K������ |
�W���m���`���E�� |
�W���m���`���E |
|
|
�@ |
|
�H�� |
�C�l������ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
picture�i�W���m���j |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
����� |
�H���A���ŁA���Y�����A���������A�����́A�����܂����Ԑ����A�����H�ׂĂ��܂��B������������������Ƃ����܂��B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
���R���^�� |
������������ |
�F�@���������z�������A���̃R���{���[�V�����A�u�����������������m�������v�A�u�����������������m�������v�A�u���������������܂ꂽ�̂��v�A�u���������������܂ꂽ�̂��v�B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|