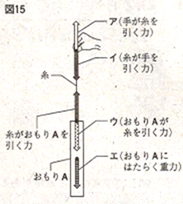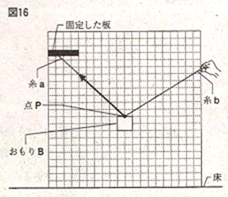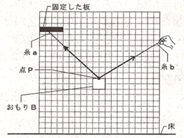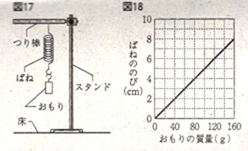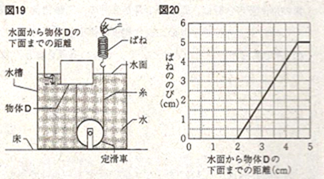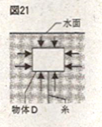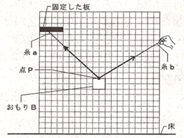| 6 |
�@�g�������������y���^���ƃG�l���M�[��������(1)~(3)�����������Ȃ����B(11�_) |
|
|
|
|
�@ |
���� |
|
���́������h���b�O����ƕ\������܂��B |
|
|
|
�@ |
|
|
(1) |
�@�}14�̂悤�ɁA������A�������������Î~�������B�������A�������������� |
|
�@ |
|
|
�ł�����̂Ƃ���B |
|
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
�@�@�}14�������^���������āA������A����������������������B������A�� |
|
�@ |
|
|
�@������������^�����������Ă���Ƃ��́A������A�ɂ͂��炭�d���������� |
|
�@ |
|
|
�@�ƁA����������A�������������������W�Ƃ��������K���Ȃ��̂��A���� |
|
�@ |
|
|
�@�A~�E��������P���I�сA�L���������Ȃ����B |
|
|
�@ |
|
|
�A |
������A�ɂ͂��炭�d���������������B |
|
|
�@ |
|
|
�C |
�����������ł���B |
|
|
�@ |
|
|
�E |
����������A���������������������B |
|
�@ |
�C |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
�A�@�}15�́A�}14�̂悤�ɁA������A�������������Î~ |
|
�@ |
|
|
�@�������Ƃ����͎��}�ł���B�}15������́A���A���A |
|
�@ |
|
|
�@������A�ɂ͂��炭�������ꂼ���\�������̂ł���B |
|
�@ |
|
|
�� |
�@�}15������������A������������p�E����p���� |
|
�@ |
|
|
�n�ɂ��������A�}15�̃A~�G�������������P���I |
|
�@ |
|
|
�сA�L���������Ȃ����B |
|
�@ |
�E |
|
|
�� |
�@�}15������������A���������Ƃ��������W�� |
|
�@ |
|
|
���������A�}15�A~�G�������������P���I�сA |
|
�@ |
|
|
�L���������Ȃ����B |
|
�@ |
�G |
|
|
|
|
�@ |
|
|
(2) |
�@�}16���Œ��������ɂ������������������ |
|
|
�@ |
|
|
��B�ɂȂ��A������B�ɂȂ�������������� |
|
|
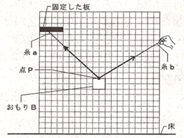
|
|
|
���߂������āA������B���Î~�������Ƃ����� |
|
|
�@ |
|
|
���}�ł���B�}16�����( �� )�́A���������� |
|
|
�@ |
|
|
��B�����������\���Ă���B���̂Ƃ��A�������� |
|
|
�@ |
|
|
����B�����������A�_P����p�_�Ƃ��āA�}16�� |
|
|
�@ |
|
|
���(�@���@�j�ł����Ȃ����B |
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
(3) |
�@�}17�̂悤�ɁA�X�^���h�̂��_�ɂ˂��� |
|
|
|
�@ |
|
|
�����A�˂ɂ�������������āA�Î~�������B |
|
�@ |
|
|
�������A�˂ɂ������邨��������������� |
|
|
�@ |
|
|
�Ȃ���A�˂̂̂т��������B�}18�́A���̂� |
|
|
�@ |
|
|
���́A������������Ƃ˂̂̂т��W���\�� |
|
|
�@ |
|
|
�����̂ł���B�������A100g�������ɂ͂��� |
|
|
�@ |
|
|
���d�������������PN�Ƃ��A�˂����������� |
|
|
�@ |
|
|
�ł�����̂Ƃ���B |
|
�@ |
|
|
�@�@�}17�̂˂ɁA������C�����������Ƃ��A�˂̂̂т�6cm�ł������B������C�������� |
|
�@ |
|
|
�@��g���B�܂��A������C�����������Ă������Ƃ��A���ʏ��ł�����C�ɂ͂��炭�d���������� |
|
�@ |
120 |
|
|
�@�́A��N�ɂȂ���l�����邩�B���ꂼ�������Ȃ����B�������A���ʏ��ł��������d���́A�n�� |
�@ |
|
|
|
|
�@���ł��d���̂U���̂P�ɂȂ���̂Ƃ���B |
|
�@ |
0.2 |
|
|
�@ |
|
|
�A�@�}19�́A������������D�� |
|
|
�@ |
|
|
�@�}17�̂˂��A������������ |
|
�@ |
|
|
�@ �������ɂ��������������� |
|
�@ |
|
|
�@�������������u�ł���B |
|
�@ |
|
|
�@�@�}19������D�́A����80g |
|
�@ |
|
|
�@�ł���A���������ƁA�X�� |
|
�@ |
|
|
�@���ƂȂ���������Qcm������ |
|
�@ |
|
|
�@����Î~����B�˂��^���� |
|
�@ |
|
|
�@�����ƁA����D���������X�� |
|
�@ |
|
|
�@���ƂȂ��^��������ł����B�}20�͂��̂Ƃ���������������D�������܂ł������Ƃ˂� |
|
�@ |
|
|
�@�̂т��W���\�������̂ł���B�������A���������������ł��A�芊�������C�͂Ȃ����̂Ƃ� |
�@ |
|
|
�@��B�܂��A������������D�������܂ł��������Tcm�ɂȂ�܂ł�����D���芊���͂Ԃ��邱 |
|
�@ |
|
|
�@�Ƃ͂Ȃ����̂Ƃ���B |
|
�@ |
|
|
���@�������������c�������܂ł�������3.5cm�̂Ƃ��A����D�ɂ͂��炭����������������N |
�@ |
|
|
�@���B�}18���}20�����ƂɁA�v�Z���������Ȃ����B |
|
�@ |
1.4 |
|
(80�{60)�� |
|
|
�@ |
|
|
���@�}21�́@�A�}19������D���������X���邱�ƂȂ��^�������߂��Ƃ��� |
|
|
�@ |
|
|
�@����D���㉺���������E�����ɂ͂��炭�����̂悤�������(�@���@) |
|
�@ |
|
|
�@���\�����͎��}�ł���B����������D�ɂ́A�����ɂ���āA�^������ |
|
�@ |
|
|
�@�����������͂��炭�B�}21�����l������A����D�ɂ͂��炭������ |
|
�@ |
|
|
�@�^���������ł������R���A����D���^�����������E�����ɂ͂��炭�� |
|
�@ |
|
|
�@�����֘A�t���āA�ȒP�������Ȃ����B�������A���(�@���@)�������� |
|
�@ |
�����́A��������������������������������������B |
|
�@���������������\������B |
|
�@ |
���E�������́A�������������������A�������������B |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|