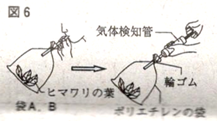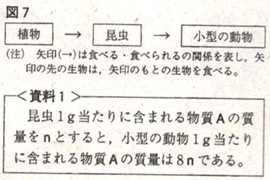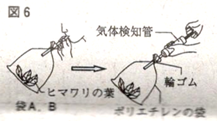| 2 |
いろいろな生物とその共通点、生物の体のつくりとはたらき及び自然と人間に関する(1)~(3) |
|
|
|
答え |
|
下の□内をドラッグすると表示されます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
の問に答えなさい。 |
(11点) |
|
|
|
|
(1) |
Sさんは、学校でイヌワラビとヒマワリを観察した。 |
|
|
|
|
① ヒマワリはなかまをふやすために種子をつくるが、イヌワラビは種子をつくらない。イヌワ |
|
胞子 |
ア |
|
|
ラビはなかまをふやすために種子ではなく何をつくるか。その名称を書きなさい。また、次の |
|
|
|
ア~エの中から、イヌワラビのように、種子をつくらない植物を一つ選び、記号で答えなさい。 |
|
|
|
ア スギゴケ |
|
イ マツ |
|
ウ イネ |
|
エ ハコベ |
|
|
|
|
|
|
|
② 図5は、ヒマワリの葉のつき方を真上から観察したときのスケッチであ |
|
|
|
葉が、重なり合っていないこと。 |
|
|
る。図5からわかる、日光があたりやすくなるためのヒマワリの葉のつ |
|
|
|
|
き方の特徴を、簡単に書きなさい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
③ 次の▭の中の文が、ヒマワリの特徴について適切に述べたものと |
|
|
イ |
|
|
なるように、文中の( あ )、( い )のそれぞれに補う言葉の組み合わ |
|
|
|
|
|
せとして正しいものを、下のア~エの中から一つ選び、記号で答えなさい。 |
|
|
|
|
|
|
|
ヒマワリは、(
あ )葉類である。茎の横断面を観察すると、維管束は( い )。 |
|
|
|
|
|
|
|
ア あ 双子 い 散在している。 |
|
イ あ 双子 い 輪のように並んでいる。 |
|
|
|
|
ウ あ 単子 い 散在している。 |
|
エ あ 単子 い 輪のように並んでいる。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
Sさんは、図6のように、同じ大きさの透明なポリエチレ |
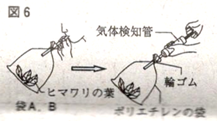
|
|
|
|
|
ンの袋A、Bに、採取したばかりのヒマワリの葉を同じ枚数 |
|
|
|
|
入れて、息をふきこみ、輪ゴムで密閉してから、袋A、Bの |
|
|
|
|
中の二酸化炭素の割合(濃度)を気体検知管で測定した。その |
|
|
|
|
後、袋Aを光のあたる場所に、袋Bを光のあたらない場所に |
|
|
|
|
放置した。数時間後、袋A、Bの中の二酸化炭素の割合(濃 |
|
表1 |
|
|
|
|
度)を気体検知管で再び測定し、袋を放置する前とそれぞれ |
|
|
|
|
袋A |
袋B |
|
|
|
|
比べた。表1は、この実験の結果をまとめたものである。 |
|
二酸化炭素の割合(濃度) |
|
|
|
減少 |
増加 |
|
|
|
|
① 葉の表皮には、二酸化炭素などの気体の出入り口としてはたらく、三日月形の2つの細胞に |
|
気孔 |
|
|
囲まれたすき間がある。このすき間は何とよばれるか。その名称を書きなさい。 |
|
|
|
|
② Sさんは、図6の実験において、袋Aの二酸化炭素の割合(濃度)が減少したのは、葉のはたら |
|
袋A |
|
|
らきによるものではないかと考えた。この考えが正しいかどうかを確かめるために、袋A、B |
|
|
葉を入れないもの |
|
|
と同じ大きさの透明なポリエチレンの袋Cを用いて、対照実験を行うことにした。このとき、 |
|
|
|
|
対照実験は、袋A、Bどちらの実験に対して条件を変えて行えばよいか。記号で答えなさい。 |
|
|
|
|
また、この対照実験は、どのように条件を変えればよいか。簡単に書きなさい。 |
|
|
|
|
③ 図6の実験において、袋Bの二酸化炭素の割合(濃度)が増加した理由を、葉のはたらきに関 |
|
|
光合成は行わず、呼吸が行われている。 |
|
|
連づけて、簡単に書きなさい。 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
Sさんは、植物と動物とのつながりに興味を持ち、 |
|
|
|
|
|
ある地方の陸上の生態系における食物連鎖について |
|
|
|
|
調べた。 |
|
|
|
|
|
図7は、Sさんが調べた食物連鎖の一部を模式的 |
|
|
|
|
に表したものである。図7の小型の動物は、昆虫な |
|
|
|
|
どを食べて有機物をとり入れている。体内にとり入 |
|
|
|
|
れた物質を分解、排出できない場合、それらの物質 |
|
|
|
|
は体内に蓄積される。資料1は、Sさんが調べた生態系の、昆虫と小型の動物に含まれる物質A |
|
|
|
|
の質量についてまとめたものである。昆虫1個体の質量を12g、小型動物の1個体の質量を |
|
|
|
|
450gとすると、450gの小型の動物1個体に含まれる物質Aの質量は、12g昆虫1固体に含ま |
|
|
12×n:450×8n= 12 : 3600 = 1 : 300 |
|
|
れる物質Aの質量の何倍か。資料1をもとに、計算して答えなさい。 |
|
|
|
|
|
生成AI |
Aさんと端末AIさんの会話 |
|
|
|
|
|
|
|
Aさん |
|
昆虫1gに含まれる物質Aの質量を、 |
1 |
n とすると、 |
|
|
|
|
|
昆虫のもつ、nはいくら。 |
|
|
端末AI |
|
昆虫の質量を教えてください。 |
|
|
Aさん |
|
昆虫の質量は、 |
12 |
g です。 |
|
|
端末AI |
|
12 |
g の昆虫に含まれる物質は、 |
12 |
nです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aさん |
|
小型動物の1個体1は、1gにつき、 |
8 |
nであり、 |
450 |
gあることから |
|
端末AI |
|
小型動物の持つ物質Aの量は、 |
3600 |
n となる。 |
|
|
Aさん |
|
昆虫1匹の持つ物質Aと小型動物1個体の持つ物質Aを比較するして。 |
|
|
|
端末AI |
|
昆虫と小型動物の割合は、 |
|
|
|
|
|
昆虫 |
12 |
n |
: |
小型動物 |
3600 |
|
|
Aさん |
|
小型動物の1個体の物質Aは、昆虫のもつ物質Aの何倍ですか。 |
|
|
端末AI |
|
小型動物の物質Aを、昆虫の物質Aでわります。 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
端末AIから |
|
|
|
|
※ 問題では、食べる食べられるに関係なく、昆虫のnと小型動物のnの比になる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|