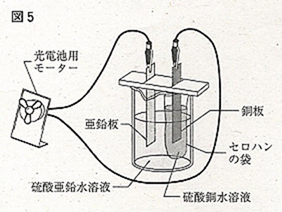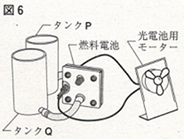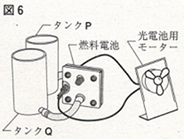| 3 |
�@���w�ω��ƃC�I���y�����w�ω������q�E���q��������(1)~(3)�������������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)�@�}�T�̂悤�ɁA�r�[�J�[�������_�������n�t�� |
|
|
|
�@���_�����n�t���������Z���n������������A���_�� |
|
|
�@�����n�t���������������A���_�����n�t���������� |
|
|
�@��������d�r������B�����d�r�́A������������ |
|
|
�@�Ɍ��d�r�p�̃��[�^�[���ڑ�����ƁA���d�r�p�̃� |
|
|
�@�[�^�[����]�����B |
|
|
|
�@�@�}�T���d�r�̂����݂���������R�����S������A |
|
|
�@�����d�p���[�^�[����]�������������@�ɂ����b |
|
|
�@���Ă���B���̂Ƃ��A���̇@~�B�������Ȃ����B |
|
|
R����@�F�@��
�}�T���d�r�́A�����̃C�I���ւ̂Ȃ�₷���ɂ���āA���������������N |
|
|
�@�@�@�@�@�������������܂��Ă�����ˁB |
|
�@ |
|
|
S����@�F�@�������ˁB���d�r�p�̃��[�^�[����]�������́A�g�p���������̃C�I���ւ� |
|
|
�@�@�@�@�@�Ȃ�₷�����W���Ă�����v����B |
|
�@ |
|
|
R����@�F�@�����������ɁA�������A�������C�I���ɂȂ�₷���}�O�l�V�E���������� |
|
|
�@�@�@�@�@�����Ă݂悤�B��������A���d�r�p���[�^�[����]�������Ȃ肻�����ˁB |
|
|
S����@�F�@���������ʐ������������Ă��A�d�q�����o�����������������肷���ꏊ���� |
|
|
�@�@�@�@�@���āA���d�r�p���[�^�[����]�������Ȃ肻�����ˁB |
|
�@ |
|
|
R����@�F�@�Ȃ�ق�
b�@�}�T�������������_�������n�t���A�}�O�l�V�E���������_�}�O |
|
|
�@�@�@�@�@�l�V�E�����n�t�������āA�����A�}�O�l�V�E�������ʐ����A�}�T�́A�����A�� |
|
|
�@�@�@�@�@�������ʐ��������������āA�����d�p���[�^�[����]�������Ȃ邩���ׂĂ� |
|
|
�@�@�@�@�@�悤�B |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@�@���_�������_�����́A�d�����ł���A�����n������z�C�I�����A�C�I�����������B�d���� |
|
���� |
|
�d���� |
|
|
�@�@�������n�����z�C�I�����A�C�I����������邱�Ƃ����Ƃ��邩�B���������������Ȃ����B |
|
�������@���n�t |
�d�����@�d�� |
|
|
�@�A�@������ ���@���������N�������w�ω����A�d�q�P���� e- �Ƃ��āA���w���������\���ƁA |
|
|
Cu2�{�@�{�@2e-�@➞�@Cu�@�ƂȂ� |
|
|
���@�����������������N�������w�ω����\�������w���������Q�l�ɂ��āA������ a �������� |
|
|
�@���N�����ω������w���������\���Ȃ����B |
|
|
b�@���̃A~�G��������A�}�T���d�r�ɂ�����A�d�����d�q���ړ��ɂ��āA�K�����q�ׂꂢ |
|
|
�@����̂��P���I�сA�L���������Ȃ����B |
|
|
�A�@�����́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |
|
|
�C�@�����́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |
|
|
�E�@�������́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |
|
|
�G�@�������́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |
|
|
�@�B�@������ b �����@���������s���ƁA���d�p���[�^����]�������Ȃ����B�������A���������� |
|
���� |
|
�����@�C�I�� |
|
�_�j�G���@�d�r |
|
|
�@�@���������ł́A���d�r�p���[�^�[����]���������g�p���������̃C�I���ւ̂Ȃ��₷������ |
|
|
�@�@�W���ꂢ�邱�Ƃ��m�F�ł����Ƃ͂����Ȃ��B�������R���ȒP�������Ȃ����B�������A���_�� |
|
|
�@�@���n�t�A���_�������n�t�A���_�}�O�l�V�E�����n�t���Z�x���̐��́A���d�r�p���[�^�[���� |
|
|
�@�@�]�������Ȃ������Ƃɂ��e�����Ă��Ȃ����̂Ƃ���B |
|
|
|
(2) |
�@S����́A���f���_�f���������邱�Ƃ��d�C�����������R���d�r�������������A�R���d�r |
|
|
�ɂ������ׂ��B����1�́A�R���d�r�������������f���_�f���̐ϔ������ׂ邽�߂ɁAS���� |
|
|
���s���������������܂Ƃ߂����|�[�g���ꕔ�����������̂ł���B |
|
|
����1 |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�����@�R���d�r�A�^���NP�A�^���NQ�A���d�r�p���[�^�[ |
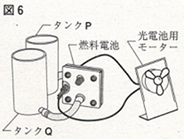
|
|
�@ |
|
|
�����@�}6�̂悤�ɁA�^���NP���C�������f8cm3���A�^���N |
|
�@ |
|
|
�@�@�@Q���C�����_�f2cm3������A���f���_�f������������B |
|
�@ |
|
|
�@�@�@�R���d�r���ڑ��������d�r�p���[�^�[����]���I��� |
|
�@ |
|
|
�@�@�@�Ă���A�^���NP�AQ���c���Ă����C�����̐����A���� |
|
�@ |
|
|
�@�@�@������������B�������A�^���NQ��������C�����_�f |
|
�@ |
|
|
�@�@�@��4cm3�A�Ucm3�A�Wcm3�������āA���l���������s���B |
|
�@ |
|
|
���� |
|
�\3�̂悤�ɂȂ����B |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�\3����A�����������f�� |
|
�\�R |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@�_�f���̐ϔ��́A�Q�F�P�ł���B |
���ꂽ���f���̐�(cm3�j |
8 |
8 |
8 |
8 |
�@ |
|
|
�@ |
|
���ꂽ�_�f���̐�(cm3�j |
2 |
4 |
6 |
8 |
�@ |
|
|
�@ |
|
�c�������f���̐�(cm3�j |
4 |
0 |
0 |
0 |
�@ |
|
|
�@ |
|
�c�����_�f���̐�(cm3�j |
0 |
0 |
2 |
4 |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
�@�@�@�����������p�������f�́A�����d�C���������������������A�ق������@�ł����f�������� |
|
|
�@�@���邱�Ƃ��ł���B���̃A~�G����A���f���������������Ƃ����K���Ȃ��̂������I�сA�L |
|
|
�@�@���������Ȃ����B |
|
|
�A�@�_����������������������M����B |
|
�C�@�_�������Y�f������������������M����B |
|
|
�E�@���_�����_���o���E�����n�t���܂���B |
�G�@���_�ɃX�`�[���E�[��(�S)�������B |
|
|
�@�A�@�R���d�r���ڑ��������d�r�p���[�^�[����]���Ă���Ƃ��A���� |
|
50 |
|
�@ |
|
|
�@�@�������f���_�f���̐ϔ��́A�Q�F�P�@�ł���A���f��1cm3�������� |
�� |
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@��̂ɂ�����������5���ł������B�\�R�����Ƃɂ����A�^���NP���� |
�� |
�d |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@������f���̐����Wcm3�ɂ����Ƃ��́A�^���NQ��������_�f���̐� |
�] |
�r |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@�����d�r�p���[�^�[����]�����������W���\���O���t���A�}�V�� |
�� |
�p |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@�����Ȃ����B�������A���d�r�p�̃��[�^�[����]���Ă���Ƃ��A���f |
�� |
�� |
25 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�@��������������������Ă������̂Ƃ���B |
|
�� |
�b |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�� |
�^ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
�b |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
(��) |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
0 |
2 |
6 |
8 |
|
|
�^���NQ������� |
|
|
�_�f���̐�(cm3) |
|
|
�@(3)�@�}�W�̂悤�ɁA�|���G�`�������������ɁA�����̐��́A���f���� |
|
|
|
���f���̐��@�@ |
a |
|
|
|
�@�@�C�����Ė����A�_�Α��u���_������ƁA���f���_�f���Q�F�P�� |
|
|
��C���̐� |
a |
�����̐� |
|
|
|
�@�@�̐����������������A�������������B�������A�|���G�`���������� |
|
|
�_�f���̐� |
b |
|
|
�@�@�����c�����C�������x���_���O���C�������x���������Ȃ�܂Ń|�� |
|
|
���f���̐� |
a-b |
|
|
�@�@�G�`�������������u�����Ƃ���A�����������͂��ׂ��t���ɂȂ�A |
|
|
|
�@�@�|���G�`���������������c�����C�����̐���28cm3�ɂȂ����B�|���G |
|
|
�_�f�F���f�@1�F2 |
|
b:a=1:2 |
|
(���@���@���f���\���ɂ���j |
���w�ω� |
|
|
�@�@�`���������������_�f�͂��ׂ����������Ƃ���ƁA�������Ƀ|���G |
|
|
�_�f�F���f�@�P�F�S |
|
b:(a-b)=1:4 |
a-b=4b |
a=5b |
(���@��C�������j |
|
|
�@�@�`���������������c���Ă������f���̐�����cm3�ł�����l����� |
|
|
|
�@�@�邩�B�v�Z���������Ȃ����B�������A��C�ɂ��_�f�����f���������܂�Ă���A���f���_�f�� |
|
�c�������f |
a-2b |
(���@���2b�@���Ƃ����f��g�p�������f�j |
|
|
�@�@�S�F�P���̐ϔ����������Ă�����̂Ƃ���B�܂��A���f���_�f�������ȊO���������N����Ȃ� |
|
|
�@�@���̂Ƃ���B |
|
�c�������f�{���f��28 |
|
(a-2b)+(a-b)=28 |
(���@a�b�@�g��Ȃ����f�j |
|
|
|
(a-2b)+(a-b)=28 |
|
���f |
|
20 |
|
(���@���f����C�����̐��j |
|
|
a=5b |
5b-2b+5b-b=28 |
|
��C |
|
20 |
|
(���@���f�{�_�f�j |
|
|
7b=28 |
|
�_�f |
�� |
4 |
|
|
b=4 |
|
���f |
|
16 |
|
(���@���f���_�f��4�{�j |
|
|
|
�g��ꂽ���f |
|
8 |
cm3 |
|
(���@���f���_�f�̂Q�{) |
|
|
�c�������f |
20-8 |
cm3 |
|
|
�c�������f |
�@ |
12 |
cm3 |
|
|
�^�u���b�g�g�p(���j |
|
|
|
|
�@ |
�@���f�A��C���̐�������(�̐���������)���������i��������j�A |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�c�����C�̂̑̐ς���A�c���Ă��鐅�f�̗ʂ����߂���@�������B |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
�c���Ă����C�����̐� |
�c���������f |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
���� |
|
|
|
�\�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
28 |
cm3 |
|
12 |
cm3 |
|
|
|
|
|
�� |
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
�g�p�����_�f���� |
|
|
|
=Y106/7 |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
��C�����܂�����f���� |
|
|
=AN107*4 |
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
��C���̐� |
|
|
|
|
=AN107+AN108 |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
12 |
�c���������f |
�@ |
�@ |
�@ |
=AN109-2*AN107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|