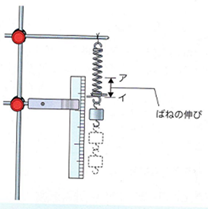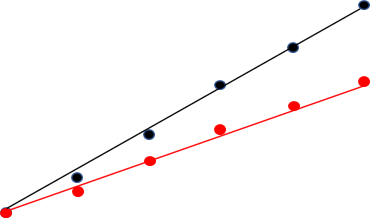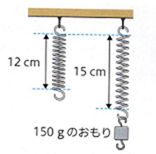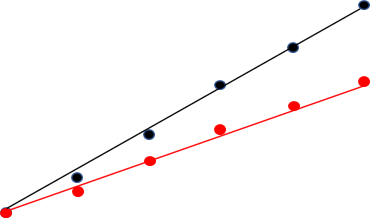| 2022.springexpangh |
�����������Ƃ˂��L�� |
�N�@ �g�@ �Ԏ���(�ȗ���) |
|
�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t |
|
�w�K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�˂�����������������Ȃ�ƁA�˂��L�т��������Ȃ�B |
|
|
|
|
�������� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�˂���������Ƃ˂��L�т�������W�ɂ���B |
|
|
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t�i�T�j |
|
�e���̂����������ό`���������́A���킦�������������B������A�t�b�N���@���Ƃ����B |
|
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
| ���̂͂��炫 |
|
�@ |
�����������Ƃ˂��L�� |
|
�܂Ƃ� |
�˂�����(���萔�������E��������������������Ƃ˂��L�т��\�������) |
|
�����������Ƃ˂��L�� |
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�����������@ |
F |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
����5 |
�e�[�} |
�˂�����������������Ȃ�ƁA�˂��L�т͂ǂ̂悤�ɂȂ邩 |
|
�@ |
|
�������� |
|
�@ |
|
�˂��L�� |
L |
|
�@ |
|
|
���@ |
1 |
�������u���g������ |
|
�@ |
|
�@ |
|
���萔 |
|
�� |
|
�@ |
|
|
�} |
|
�˂� |
|
�@ |
|
���������(���j |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
�@ |
�t�b�N���@�� |
|
�@ |
|
|
|
|
�@ |
|
����������� |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
|
�@ |
|
L |
�� |
�� |
�~ |
F |
|
|
�@ |
|
|
2 |
�˂��L�т���������B |
|
|
�@ |
|
���������� |
0 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
�@ |
|
�\�� |
|
���� |
|
���� |
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
�˂����L�� |
0 |
3.8 |
7.9 |
12.2 |
16.3 |
20.4 |
|
�@ |
|
�˂��L��L |
���萔�� |
����������F |
�@ |
|
|
|
�@ |
|
��b���L�� |
0 |
2.4 |
5.2 |
7.9 |
10.6 |
13.2 |
|
�� |
|
13 |
cm |
13 |
|
1 |
N |
�@ |
|
|
3 |
��������������₵�Ă����A�˂��L�т� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
=AQ14*AT14 |
|
�@ |
|
|
��������B |
|
|
�@ |
|
|
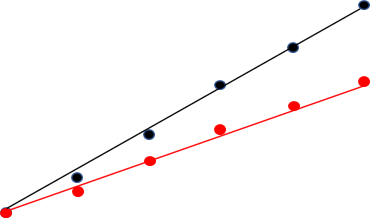
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���� |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
�@ |
|
15 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
4 |
�����̂������˂��Ł@�P~3�@������������B |
|
|
�@ |
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
���萔�@�� |
|
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
�@ |
|
�� |
10 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
20.375 |
|
��20 |
|
0.05 |
N/cm |
|
|
�@ |
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
�L |
5 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
��b |
�@ |
�@ |
|
���萔�@�� |
|
|
���� |
|
�@ |
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
13 |
|
13 |
|
0.07692 |
N/cm |
|
|
���������(���j |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
�@ |
|
(cm) |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
����������� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
0 |
|
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
|
|
���������� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�����������@(N�j |
|
|
�˂����L�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�O���t����A�����������Ƃ˂��L�т́A�u����v����B |
|
|
��b���L�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�˂� |
���萔�@��20cm/N |
0.05 |
N/cm , |
�˂� |
���萔�@13cm/N |
0.08 |
N/cm |
|
|
�@ |
|
|
�O���t�� |
(cm) |
|
�@ |
|
�e���̂����������ό`�����������́A�����������������B |
|
|
�@ |
�@ |
10 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
������A�u�t�b�N���@���v�Ƃ����B |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�t�b�N���@�� |
|
|
8 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�f�[�^ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
����������(N) |
0 |
0.5 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
|
�@ |
|
|
�� |
6 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�˂��L��(cm) |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
�@ |
|
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
���萔�@�S |
|
�@ |
|
|
�L |
4 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�����������@ |
F |
|
�@ |
|
|
�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
�˂��L�� |
L |
|
�@ |
|
|
2 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
���萔 |
|
�� |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�t�b�N���@�� |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
L |
�� |
�� |
�~ |
F |
|
�����S |
|
�@ |
|
|
0 |
|
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
�@ |
�@ |
�˂��L��(cm) |
���萔�� |
��������������(N�j |
|
�@ |
|
|
|
�����������@�iN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
8 |
cm |
4 |
|
2 |
N |
|
�@ |
|
|
�l�@ |
|
�@ |
�@ |
|
=AB43*AE43 |
|
�@ |
|
|
�˂��L�т������W |
|
�@ |
�@ |
|
F |
= |
L/a |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
|
F (N) |
|
����萔 a |
�����˂��L��(cm) |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
3 |
N |
4 |
|
12 |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
����AI�@ |
|
A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |
|
|
�@ |
����AI�A |
|
A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |
|
|
A���� |
|
���̂������������������ |
|
�@ |
|
|
�^�u���b�g(AI) |
��������������˂͂ǂ̂悤�Ȃ˂ł����B |
|
�@ |
|
A���� |
|
�˂��g���������̂͂������������� |
|
|
A���� |
|
����10�����邷��12cm�ɂȂ�A����20�����邷��14cm�ɂȂ�܂��B |
|
�@ |
|
�^�u���b�g(AI) |
��������������˂́A�ǂ̂悤�Ȃ˂ł����B |
|
|
�^�u���b�g(AI) |
��������邵���Ƃ����S���������������Ă��������B |
|
�@ |
|
A���� |
|
�˂�50�~�d�����邷�� |
12 |
cm�ɂȂ�A500�~�d�݂��邷�� |
|
|
A���� |
|
�S���������́A |
15 |
cm�@�ł��B |
|
�@ |
|
|
|
|
15 |
cm�ɂȂ�܂��B |
(50�~�d�� |
4 |
g �A500�~�d�� |
7 |
g �Ƃ���B) |
|
|
�@ |
|
�^�u���b�g(AI) |
��������邵���S���������������Ă��������B |
|
|
�^�u���b�g�� |
�˂����� |
������� |
10 |
���邷�� |
12 |
cm |
�ɂȂ� |
�@ |
|
�@ |
|
A���� |
|
�S���������́A |
20 |
cm�ł��B |
|
|
�v�Z�� |
|
�@ |
|
|
������� |
20 |
���邷�� |
14 |
cm |
�ɂȂ� |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�������� |
10 |
g |
�ŁA |
2 |
cm |
�̂т� |
|
�@ |
|
�@ |
|
�^�u���b�g�� |
�˂����� |
50�~�d�����邷�ƁA |
12 |
cm�ɂȂ� |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
|
|
=L58-L57 |
|
=P58-P57 |
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�v�Z�� |
|
�@ |
|
|
500�~�d�����邷�ƁA |
15 |
cm�ɂȂ� |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
�˂����� |
10 |
cm |
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�������� |
|
3 |
g���A |
3 |
cm�L�т� |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
=P57-N59 |
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
=AO55-AK55 |
=AK60-AK59 |
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
�S���������A |
15 |
cm |
|
�˂��L�сA |
5 |
cm |
|
�@ |
|
�@ |
|
�˂��L�сA |
1 |
���� |
|
1 |
����1cm�L�т�B |
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
=J55 |
|
|
|
|
|
=K63-K61 |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
=(AK60-AK59)/AH61 |
=AH61/AK61 |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
������������A |
25 |
�� |
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�˂������A |
8 |
cm |
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
=(R63/N59)*10 |
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
=AK59-(AH63*AK55) |
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
���m�̂�����������A |
12 |
g |
|
|
|
�@ |
|
|
�����l�p�����h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
=(AF57-AH65)*AL63 |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�^�u���b�g(AI) |
���̂˂ɂ邵����������������A |
25 |
�� |
�ł��B |
|
�@ |
|
�����l�p�����h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |
|
|
�@ |
|
�^�u���b�g(AI) |
���̂˂ɂ邵����������������A |
12 |
�� |
�ł��B |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
| ��� |
|
���Ƃ˂��L�� |
|
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@�}�̂悤�ɁA����12cm�̂˂�150���̂�������邵���Ƃ���A�˂������́A15cm�� |
|
|
�Ȃ����B�������������Ȃ����B�������A100���������ɂ͂��炭�d������������1�m�Ƃ��A�� |
|
|
���������l���Ȃ����̂Ƃ���B |
|
�} |
|
|
|
�@ |
�@�˂̂̂т����������̂��������ɂ́A�ǂ̂悤�� |
|
|
�W�����邩�B |
|
|
|
��� |
|
|
|
�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |
|
|
�A |
�@���̂˂��Pcm�L���̂��K�v����������������N���B |
|
|
0.5 |
N |
|
�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |
|
|
�B |
�@��������lj�����ƁA�˂�������17cm�ɂȂ����B���̂Ƃ��A�lj������������������ |
|
|
�������B |
|
100 |
�� |
|
�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |
|
|
�C |
�@�����˂ɁA���ʏ���150���̂�������邵���Ƃ���B���̂Ƃ��˂��L�т́A��cm |
|
|
�ɂ܂���l�����邩�B�������A���ʏ��ł��d�������������n������1/6�Ƃ���B |
|
|
0.5 |
cm |
|
�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |
|
25 |
|
|
|
|
|
| AI���c�����t |
|
| �˂ɉ����͂��傫���Ȃ�ƁA�˂̐L�т͑傫���Ȃ�B |
|
| �˂ɉ����͂Ƃ˂̐L�т͔��̊W�ɂ���B |
|
| �e���̂��镨�̂̕ό`�̑傫���́A���킦���͂ɔ�Ⴗ��B������A�t�b�N�̖@���Ƃ����B |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|