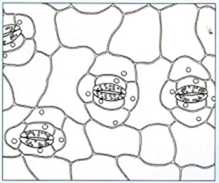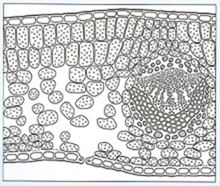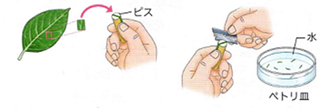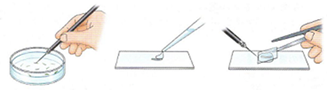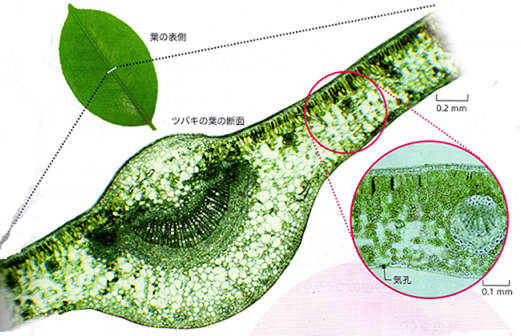| 2023.leafgh |
|
|
葉のつくり |
|
|
年 組 番氏名(省略可) |
人工知能(AI)に残す言葉 |
|
学習 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ツユクサの葉の裏側には、多数の気孔がある。 |
|
|
切り取り |
|
|
|
|
|
ツバキの葉の断面には、水や葉でできた養分の通る管がある。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人工知能(AI)に残す言葉(控) |
|
水は、道管を通り、葉の気孔から蒸散する。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 葉のつくり |
|
葉のつくり |
|
|
|
|
| 観察4 |
葉の表皮と断面 |
|
|
葉の表皮と断面 |
|
|
|
テーマ |
水が通る場所を葉のつくりから調べる。 |
|
|
結果(例) |
|
|
葉の表皮や断面にはどのようなつくりが見られるか。 |
|
|
|
ツユクサの葉の表皮(裏側)スケッチ |
|
ツバキの葉の断面のスケッチ |
|
|
方法 |
1 |
葉の裏側の表皮を観察する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ツユクサの葉の裏側に切れ目を入れ、 |
|
|
|
|
|
葉脈をつまんで表皮をはぎ取る。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表皮のプレパラートをつくり、顕微鏡で |
|
|
|
|
|
観察する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
葉の断面を観察する。 |
|
|
|
|
|
ツユクサの葉の表皮(裏側) |
|
ツバキの葉の断面 |
|
|
ピスに縦に割れ目をつくり、 |
|
|
|
|
葉の裏側には、細長い2つの細胞が |
葉の断面には、細胞が束にな |
|
|
そこにツバキなどの葉の一部を |
|
|
|
|
向かい合っている穴がある。 |
|
っている部分がある。 |
|
|
切り取ってはさみ、できるだけ |
|
|
|
|
|
うすく切り取る。 |
|
|
|
|
|
|
この穴から蒸散していると考えられ |
この細胞の束が水の通り道と |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
る。 |
|
|
|
|
|
|
考えられる。 |
|
|
|
|
|
うすく切った切片を選んで、プレパラート |
|
|
|
|
をつくり、顕微鏡で観察する。 |
|
|
|
|
|
穴の部分を「気孔」という。 |
|
細胞の束を「維管束」という。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
気孔は、「酸素」「二酸化炭素」「水蒸気」 |
|
維管束には、「道管」「師管」が通っている。 |
|
|
結果 |
|
ツユクサの葉の表皮(裏側)スケッチ |
|
ツバキの葉の断面のスケッチ |
|
|
|
の出入が行われる。 |
|
道管 : 水を輸送する管がある。水の他に、無機養分の通り道にもなっている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気孔は、葉の裏側に多い。 |
|
師管 : 葉でつくられた養分を運ぶ管がある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ツバキの葉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
葉の断面 |
|
|
|
|
気孔 |
|
|
参考資料 |
|
|
|
|
|
気孔 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スケッチの部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孔辺細胞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
|
|
| AIに残す言葉 |
|
| ツユクサの葉の裏側には、多数の気孔がある。 |
|
| ツバキの葉の断面には、水や葉でできた養分の通る管がある。 |
|
| 水は、道管を通り、葉の気孔から蒸散する。 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|