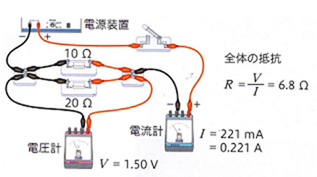| 2023.12.01
resistance22 |
抵抗の合成(並列) |
年 組 番氏名(省略可) |
人工知能(AI)に残す言葉 |
|
|
学習 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回路に抵抗を並列につなぐと全体の抵抗が小さくなる。 |
|
|
切り取り |
|
|
|
|
|
|
|
|
並列つなぎの抵抗では、全体に流れる電流が大きくなる(電流は面積に比例) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
人工知能(AI)に残す言葉(控) |
|
並列つなぎ抵抗R1、R2と全体の抵抗Rの関係は、(1/R)=(1/R1)+(1/R2)となる。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回路の抵抗 |
|
|
抵抗の並列つなぎ |
|
|
|
|
B 抵抗のつなぎ方と抵抗の大きさ(電気器具には抵抗を2個以上組み合わせた回路が多い) |
|
|
|
抵抗を並列につなぐと、回路に電流の流れる部分が増える。 |
|
|
抵抗の並列つなぎ(抵抗を2個、並列につないだ場合の全体の抵抗) |
|
|
|
換言すると、回路を流れる全体の電流が大きくなる。 |
|
|
回路に20Ωと10Ωを並列につないだ場合 |
|
|
|
|
|
|
左図のように電源電圧1.5Vに抵抗を2個 |
|
|
抵抗: 抵抗(R)は、流れにくさを表す。 (1/R)抵抗の逆数は流れやすさを表す |
|
|
|
並列につなぐ |
|
|
|
R |
|
1 |
|
|
|
電源電圧 1.5V |
|
|
|
|
R |
|
|
|
10Ωの部分の電圧
1.5V (※並列回路の電圧から) |
|
|
|
流れにくさを表す |
流れやすさを表す |
|
|
|
20Ωの部分の電圧
1.5V ( 並列回路の電圧から) |
|
|
|
|
10Ωに流れる電流を計算すると(※オームの法則から) |
|
|
抵抗を並列につなぐと、流れる部分が増え、電流が流れやすくなる。 |
|
|
|
0.15 |
A |
となる( 1.5V、10Ωから) |
|
|
|
|
20Ωに流れる電流を計算すると(※オームの法則から) |
|
|
抵抗の並列 : 電流が流れやすい。 |
|
|
|
0.075 A |
となる( 1.5V、20Ωから) |
|
|
並列回路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
電流計に流れる電流は、 |
|
|
|
全体の電流の大きさ = 各部分の流れやすさの和 |
|
|
計算値 |
0.225 A |
( 0.15+0.075から ) |
|
|
|
|
1 |
= |
1 |
+ |
1 |
|
|
|
|
|
測定値 |
0.221 A |
(※0.221≒0.225 誤さ範囲) |
|
|
|
|
R |
R1 |
R2 |
|
|
となる。 |
|
|
全体の抵抗(電流(計算値=測定値) 0.225A)と電圧(測定値1.5V)から |
|
|
|
|
抵抗(Ω)は、
6.7 Ωとなる。 |
(並列回路全体の抵抗は、どちらの抵抗より小さくなる。) |
|
|
|
|
|
|
|
電源(電圧1.5V)に抵抗を並列(R1、R2、)につないだときの、電流の大きさ。 |
|
|
|
|
抵抗 |
|
R1に流れる電流 |
1.5÷R1 (1.5/R1) |
A |
|
|
|
|
R2に流れる電流 |
1.5÷R2 (1.5/R2) |
A |
|
|
|
|
|
|
|
全体の電流 |
|
(1.5/10)+ (1.5/20) |
0.225 |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抵抗R1、R2、電圧を入力すると、並列回路全体の抵抗を計算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 黄色の部分に入力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1 |
R2 |
|
全体R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抵抗(Ω) |
|
2 |
3 |
1.2 |
|
計算処理:オームの法則 |
|
|
|
|
|
|
電圧(V) |
|
入力 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
=H33/H32 |
R1側電流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=J33/J32 |
|
R2側電流 |
|
|
|
|
|
電流(A) |
計算処理 |
0.75 |
0.5 |
1.25 |
|
|
=H35+J35 |
全体電流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=H33/M35 |
全体抵抗R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
= |
1 |
+ |
1 |
|
1 |
= |
1 |
+ |
1 |
|
|
|
|
R |
R1 |
R2 |
|
R |
10 |
20 |
|
|
|
|
R |
= |
10*20 |
|
|
|
|
10+20 |
|
R= |
6.666667 |
|
|
|
|
≒ |
6.7(Ω) |
|
|
|
|
|
|
|
抵抗R1、R2を入力すると、全体の抵抗Rを計算する。 |
|
1 |
= |
1 |
+ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R |
R1 |
R2 |
|
|
|
|
|
※ R1、R2を黄色の部分に入力 |
|
|
|
|
|
1 |
= |
R2 + R1 |
|
|
|
|
|
|
|
R1 |
R2 |
|
全体の抵抗R |
|
|
R |
R1 × R2 |
|
|
|
|
|
|
抵抗(Ω) |
10 |
15 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R |
= |
R1・R2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1+R2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
別記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
実験 |
|
抵抗2つを並列につないだ回路をつくり、全体の抵抗の大きさを調べる |
|
|
|
|
方法 |
|
R |
|
|
右図の回路をつくり、 |
|
|
|
R1 |
|
|
|
|
|
|
|
20Ω |
|
|
|
|
R1、R2、Rを測定する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30Ω |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 |
|
|
|
|
|
結果 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R |
|
|
抵抗(Ω) |
20 |
30 |
12 |
|
|
考察 |
|
並列回路の全体の抵抗は、次の式で表される。 |
|
|
(1/R) = (1/R1) + (1/R2) ・・・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生成AI |
|
|
Aさんとタブレット(AI)の会話 |
|
|
|
Aさん |
|
2つの抵抗を並列につないだ時の全体の抵抗の大きさを教えて |
|
|
タブレット(AI) |
それぞれの抵抗の大きさを教えてください |
|
|
Aさん |
|
1つは、 |
10 |
Ω |
です。 |
|
|
もう一つは、 |
15 |
Ω |
です。 |
|
|
| タブレットが |
並列回路の全体の抵抗は、 (1/R) = (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) ・・・ です。 |
|
| 並列を合成した |
|
|
R1 |
10 |
Ω |
|
R2 |
15 |
Ω |
|
R |
6 |
Ω |
|
|
| 抵抗を計算しま |
|
式 |
|
1/R |
0.166666667 |
|
|
|
|
|
|
| す。 |
|
|
|
|
|
|
=(1/K77)+(1/K78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=1/H82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全体の抵抗は、 |
6 |
となります。 |
|
|
|
|
上の□の中を、ドラッグすると計算式が表示されます。 |
|
|
タブレット(AI) |
全体の抵抗は、 |
6 |
Ω |
です。 |
|
|
|
AIに残す言葉 |
|
|
回路に抵抗を並列につなぐと全体の抵抗が小さくなる。 |
|
|
並列つなぎの抵抗では、全体に流れる電流が大きくなる(電流は面積に比例) |
|
|
並列つなぎ抵抗R1、R2と全体の抵抗Rの関係は、(1/R)=(1/R1)+(1/R2)となる。 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|