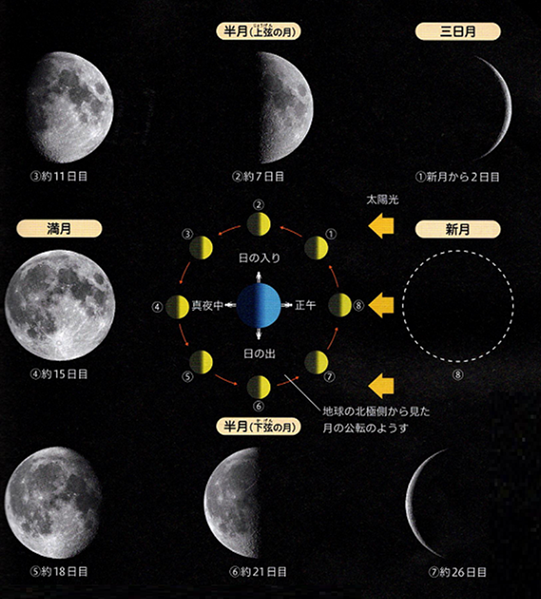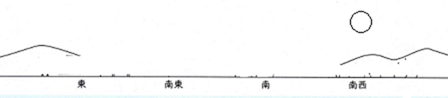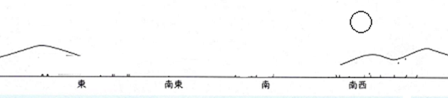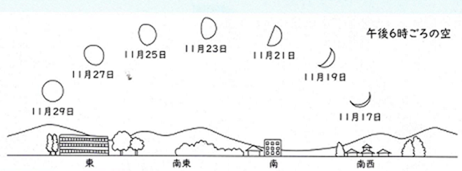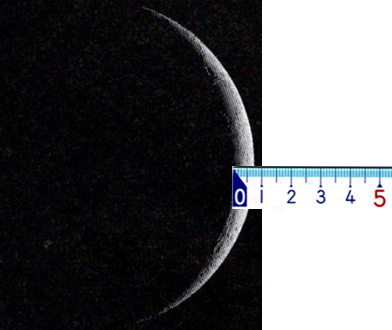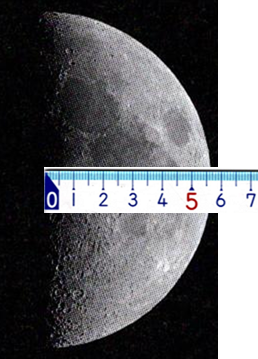| 2023.planetandmoongh |
�����f�����^�� |
|
�N�@�g�@�@�Ԏ���(�ȗ���) |
�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t |
|
�w�K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
����������������A�����n���̂܂����܂���Ă���B�������] |
|
|
�������� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
|
���]�A���z�����]�A�n�������]�A�������]�A���]�A�������]�A�n�������]�B |
|
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t�i�T�j |
|
�V���́A���z�n�̋�͂̒��̈ړ��ȂǑS�Ă��V���A���q���^�����Ă���B |
|
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
| �����^���������� |
|
�����^���������� |
|
|
�����`���ʒu���ω� |
|
�@ |
�����`���ʒu���ω� |
|
| �ώ@2 |
�����`���ʒu���ώ@ |
|
�@ |
���������������] |
|
|
�e�[�} |
���v�����������`���ʒu���ώ@����B |
|
�@ |
|
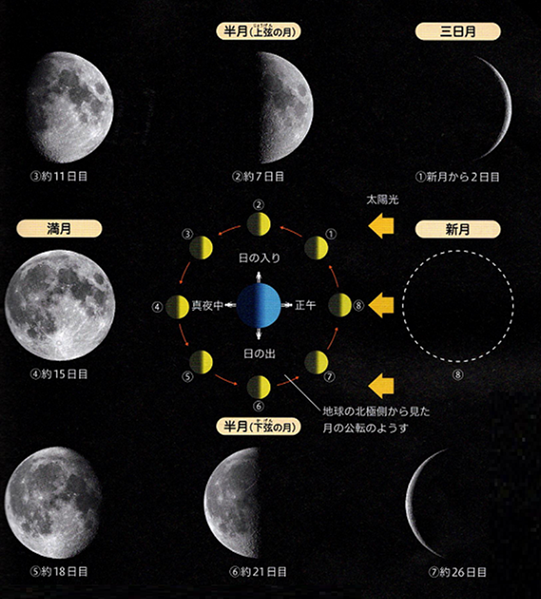
|
|
|
���v�������������������������������Ƃ��A�`���ʒu���ǂ̂悤���ω����Ă������B |
|
�@ |
|
|
���@ |
1 |
�@�������i�F���L�^����B |
|
�@ |
|
|
���邢���������� |
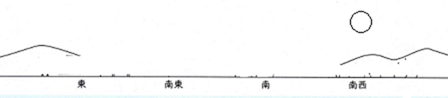
|
|
�@ |
|
|
���������n������ |
|
�@ |
|
|
�������i�F���X�P |
|
�@ |
|
|
�b�`����B |
|
�@ |
|
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
�@ |
|
|
2 |
�@�����`���ʒu���L�^����B |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
���� |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
|
�@ |
|
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
�������� |
|
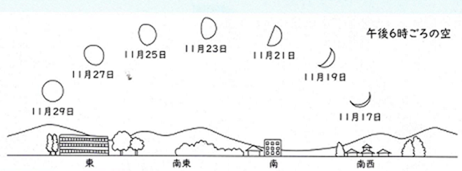
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
|
�@ |
|
������ |
�@���z�������(�����j���n����������������B |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@�n�������������Ă���Ƃ���������A�����Ă��Ȃ��Ƃ�������B |
|
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
�@ |
|
�n���͎��]���Ă��āA���Ɩ邪���݂ɂ���B�i���]���Ȃ������]���Ă���j |
|
|
�@�������������������ώ@����ƁA�������������ʒu�������B |
|
�@ |
|
�@���z�A���A�n�����W�B���z�����]���A�������]���A�n�������]������B |
|
|
�@����6���ɂ͂��������ړ����Ă����悤��������B�܂��A���������Ȃ��Ă��� |
|
�@ |
|
���]���Ă����n���������āA���z��������������������Ƃ��A�G���V��(���������Ȃ��j |
|
|
�您����������B |
|
�@ |
|
�F���������邢�O�����A�@�E�����邢�O�����A��������B |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
�@�����n���̂܂����܂��(�������]�j�̂��߇@����A���ʒu��3~4�����x���ړ����� |
|
|
����ƁA�n�����������������P���Ă��������������Ȃ�B��15�������z�A�n���A���� |
|
|
������������ |
|
�e�[�}�@�@�O�����A�㌷�������摜����A�u�V������E�V���܂Łv�������v�Z���悤�B |
|
�ʒu�W�ɂȂ�(�G����C���ʒu���ړ��j�A�n������������������B |
|
|
���@ |
|
�O�����A�㌷�����܂ł́A���������邢�������������͂���B |
|
�@�����n���̂܂�����30����1�T����B��������킹���悤�����͂P�����]����B |
|
|
�����ƁA���邢���������������ׂ�B |
|
���̂��߁A�n��������������������������������������B |
|
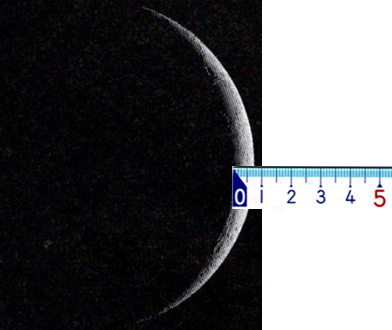
|
|
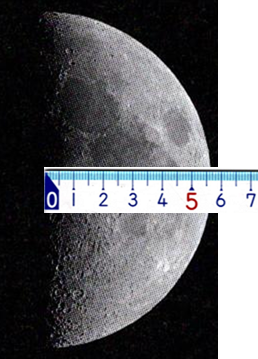
|
|
���́A�n�����������o�����V��(�q���j���l������������₷���B |
|
|
�O���� |
|
�㌷���� |
|
|
�V������Q���� |
|
|
|
|
|
|
|
�V������V���� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�}�@���ȏ��@����{�}������ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
���� |
|
��}����A�O�����E�㌷�����܂ł����������邢������������ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�V�� |
�O���� |
�㌷ |
���� |
���� |
�O���� |
�V�� |
|
|
�@ |
|
�V����������� |
0 |
2 |
7 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
���邢������ |
0 |
7 |
56 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
����(mm�j |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�l�@ |
|
|
����AI |
|
A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |
|
|
|
A���� |
|
���������������摜����A�������]�ɂ��������������ׂĂ��������B |
|
|
|
|
�^�u���b�g(AI) |
�O���������邢�����������ƁA�O�����܂ł������������Ă��������B |
|
|
|
|
�܂��A�㌷���������邢�����������ƁA�㌷�����܂ł������������Ă��������B |
|
|
A���� |
|
�O���������邢�����������́A |
7 |
mm |
�A������ |
2 |
���@�ł��B |
|
|
|
|
�܂��A�㌷���������邢�����������́A |
57 |
mm |
�A������ |
7 |
���@�ł��B |
|
|
|
|
|
��}����A�O�����E�㌷�����܂ł����������邢������������ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�V�� |
�O���� |
�㌷ |
���� |
���� |
�O���� |
�V�� |
|
|
�V����������� |
0 |
�@ |
7.125 |
14.25 |
21.375 |
�@ |
29.5 |
|
|
���邢������ |
0 |
�@ |
57 |
114 |
57 |
�@ |
0 |
|
|
|
|
|
|
����(mm�j |
�@ |
|
|
| �@�^�u���b�g�� |
�O�������㌷�������������܂ł��������v�Z�������� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
| �f�[�^�������� |
�@ |
�f�[�^����A�O�����͂Q���������邢������������7mm�@�@�P���@3.5mm |
|
|
|
|
�@ |
|
| ����A�v�Z�� |
�@ |
�@�@�@�@�@�@�㌷������7�������邢������������56mm�@�@�P���@8mm |
|
|
|
|
|
�@ |
|
| �܂��B |
|
�@ |
�i���@�O���������邳�́A�����Ȗ����������������������邳�ŁA�����͂��������邢�����������j |
|
|
�@ |
���̂��Ƃ��� |
�������]���������߂�ɂ́A�㌷������7����56mm�����邢�������������g�p |
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
�O���� |
���邢���������� |
�@ |
|
���� |
�@���O�������\������Ȃ�����������A�f�[�^������Ȃ��B |
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�㌷���� |
���邢���������� |
57 |
|
���� |
7.125 |
|
�㌷�����@�P�� |
8.1429 |
mm |
�@ |
|
|
�\ |
|
|
|
�V�� |
�O���� |
�㌷���� |
���� |
�������� |
|
�V�� |
|
|
|
�@ |
|
|
���� |
|
|
|
0 |
|
7.125 |
14.25 |
21.375 |
|
28.5 |
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=L89*2 |
=L89*3 |
|
=L89*4 |
|
|
|
�@ |
|
|
���邢���� |
|
0 |
�@ |
57 |
114 |
57 |
|
0 |
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
=J87*8 |
=L91*2 |
=L91 |
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
���邳����������� |
0 |
|
7.125 |
14.25 |
21.375 |
|
29.5 |
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
=L91/8 |
=N91/8 |
=N93+(L91/8) |
=((L91+N91+P91)/8)+1 |
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���@+1�́A�V����1�����ł��B |
|
|
�@ |
|
|
�����n��������(���])�ɂ����������́A�� |
29.5 |
�� |
�ł��B |
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
�l�@2 |
�@�O�������㌷�������d�˂�ƁA�����������������A�����ĂƂ��������������\�������B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
���̂��Ƃ���A�O�����́A���邢�������Z���B�e����Ă���B |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
���́��������h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�^�u���b�g(AI) |
�����n���̂܂����܂��(���])�ɂ����������ͤ�� |
29.5 |
�ł��B |
|
|
| AI���c�����t |
|
| ���̖�����������A���͒n���̂܂����܂���Ă���B���̌��] |
|
| ���]�A���z�̎��]�A�n���̎��]�A���̎��]�A���]�A���̌��]�A�n���̌��]�B |
|
| �V�̂́A���z�n�̋�͂̒��̈ړ��ȂǑS�Ă̓V�́A���q���^�����Ă���B |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|