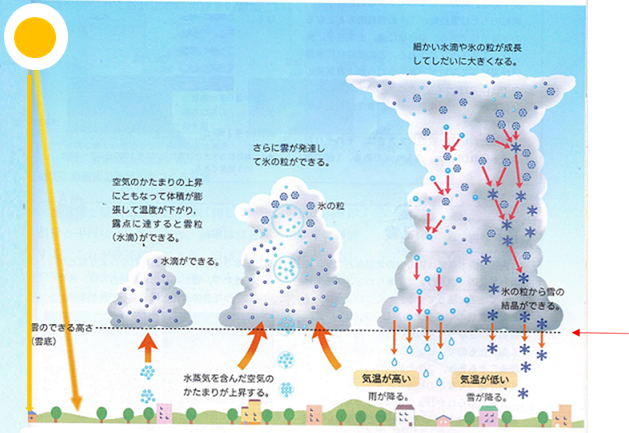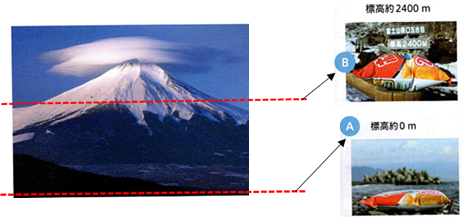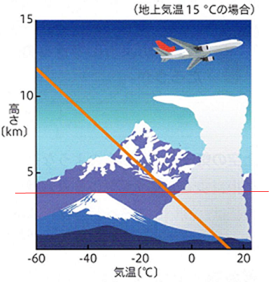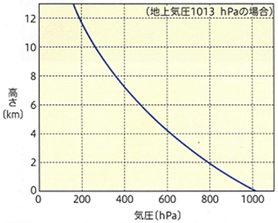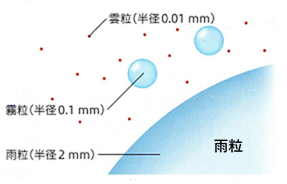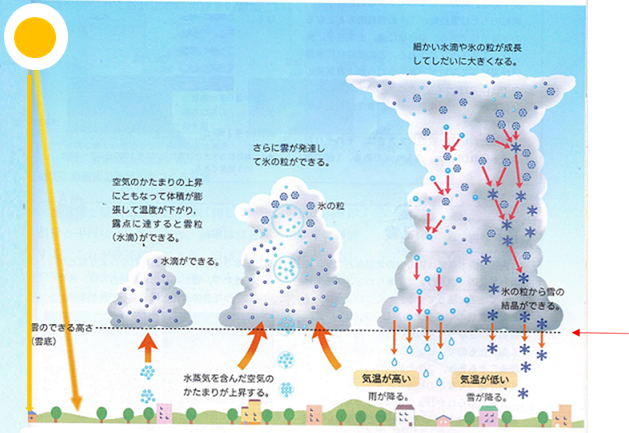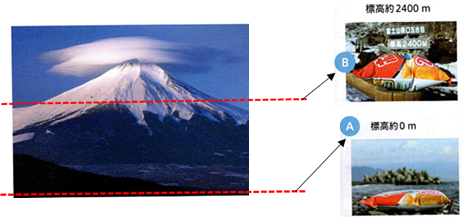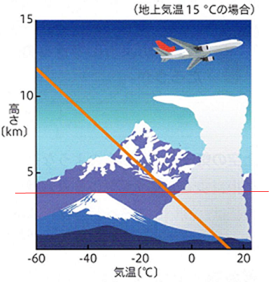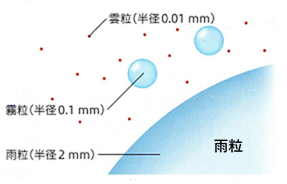| 2023.01.22 steamgathergh |
雲のでき方 |
|
年 組 番氏名(省略可) |
人工知能(AI)に残す言葉 |
|
学習 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高い山の上の方は、気圧が低い。(酸素ボンベを持参) |
|
|
切り取り |
|
|
|
|
|
高い山の上の方は、温度が低い。(凍傷、防寒対策) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人工知能(AI)に残す言葉(控) |
|
水の状態変化、液体から気体(水蒸気)になるときに熱を奪う。(気化熱) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水蒸気が水(液体)になるとき熱を出す。空気がさらに上昇する(積乱雲)。 |
|
| 雨や雲のでき方 |
|
雨や雲のでき方 |
|
|
|
上空の気圧 |
|
|
上空の気圧、温度 |
|
|
既習事項 |
|
身のまわりの空気には質量があり、重力に引かれて大気圧が生じている。 |
|
|
|
|
上空にいくほど、空気がうすく、気圧が低い。(空気の層が少なくなるため) |
|
|
雨や雪 |
|
|
太陽放射を受けると、温度が上がり、暖かい空気は上昇する。 |
|
|
|
雲をつくる水滴や氷の粒は小さく、上昇気流で落ちてこない。 |
|
|
上昇気流が起きている場所(低気圧)は天気が悪い。 |
|
|
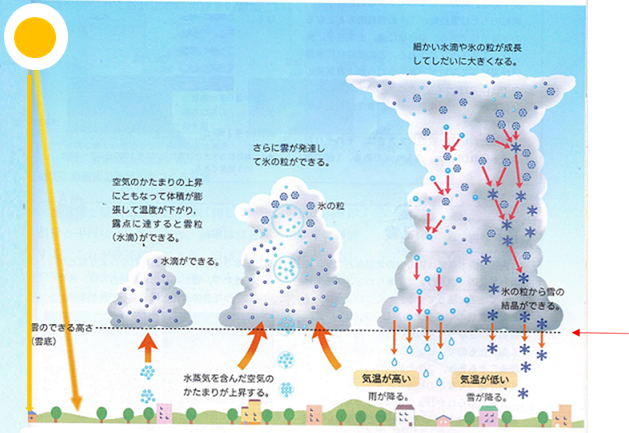
|
粒が大きくなると、上昇気流では支えられず落下する。この水滴が雨や雪となる。 |
|
|
下降気流が起きている場所(高気圧)は天気が良い。 |
|
|
|
|
空気を冷やすと、水蒸気が集まり、露点に達すると、水滴ができる。 |
|
|
|
|
|
|
|
確認 その1 気圧 |
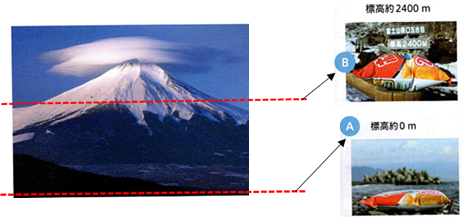
|
|
|
|
|
ポテトチップスの袋が |
|
|
|
|
膨らんでいる |
|
|
|
|
|
|
| 2400m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0m |
|
ポテトチップスの袋 |
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
店にある状態 |
|
|
|
|
山の上は気圧が低い。 |
|
|
|
雲底 |
|
|
|
|
|
|
確認 その2 上空の温度 |
|
|
|
|
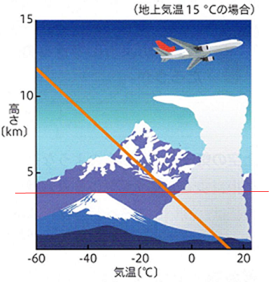
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空気の上昇 |
|
|
雲が発達 |
|
|
水滴や氷の粒が落下とともに |
|
|
|
|
|
露点に達し雲粒 |
|
さらに空気の上昇 |
|
大きくなる。温度が低いと雪 |
|
|
|
|
|
ができる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
|
雨粒や雲粒の大きさ |
|
|
|
|
|
|
|
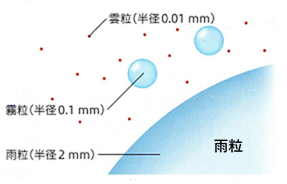
|
|
あまつぶ |
|
|
|
|
|
雨粒の大きさ : 半径2mm程度 |
|
|
|
|
|
くもつぶ |
|
|
|
|
|
雲粒の大きさ : 半径0.01mm程度 |
|
|
高さと気圧の関係 |
|
|
|
きりつぶ |
|
|
高さと気温の関係 |
|
気圧200hPaでは、高さ11.5km付近 |
|
|
|
霧粒(水滴)の大きさ:半径0.1mm程度 |
|
|
地上気温15℃の場合 |
|
気圧400hPaでは、高さ7km付近 |
|
|
|
ぎょうけつかく |
|
|
富士山3.8km付近では、-10℃くらい |
|
富士山3.8km付近は、約600hPaくらい |
|
|
|
凝結核の大きさ : 雲粒の1/1000 |
|
|
|
|
|
図 教科書 大日本図書から |
|
|
|
|
|
から 1/10 程度 |
|
|
|
|
|
1個の雨粒 : 霧粒 800万個 |
|
凝結核 : 土壌粒子、火山灰、工場の煙 |
|
|
|
|
|
1個の霧粒 : 雲粒 8000個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|