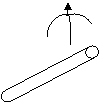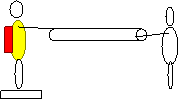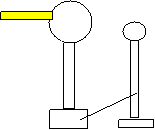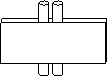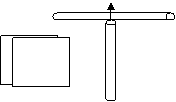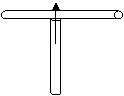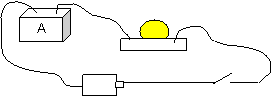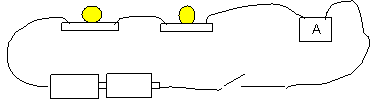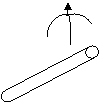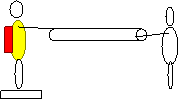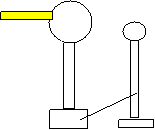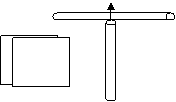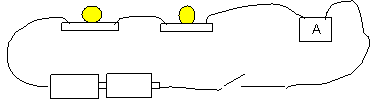| D7000 |
�e�[�} |
���d�C�������悤 |
|
|
|
|
D7000 |
|
�e�[�} |
�Ód�C�������悤 |
|
|
�d�C�N���Q |
�e�[�} |
�Ód�C�������悤 |
|
|
|
|
|
|
�e�[�} |
�Ód�C�������悤 |
|
|
|
|
|
|
|
�e�[�} |
�Ód�C�����ׂ� |
|
| �S�����T�� |
���� |
�X�g���[�@�A�@�V�[�g�@�A�@�s�� |
|
��]�X�g���[ |
|
���� |
�r�j���p�C�v�@�A�@�r�j�[���e�[�v���������{���{�� |
|
���� |
|
|
�l���u���� |
|
���� |
|
|
������ |
|
���� |
|
|
|
���@ |
|
|
���@ |
|
|
���@ |
|
|
���@ |
|
|
���@ |
|
|
|
�P�@�d�C��������Ƃ��́A�ǂ�ȂƂ��@�E�E�E�E�E�E |
|
|
�@�@�P�@�r�j���e�[�v�Ń{���{��������A�e�B�b�V���y�[�p�[ |
|
|
�P�@��l���u������ |
�Z�[�^���p |
|
|
�P�@�������~���ł����� |
|
|
�Ód���d���������u���u���������Â��� |
|
|
�@�@�@�@�ł悭�������āA�ѓd������ |
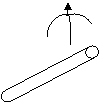
|
|
|
�@�@���� |
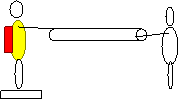
|
|
|
�@�@�ѓd������ |
|
|
|
�u�������ω����݂� |
|
|
���d |
�Ód�C |
|
|
|
|
�r�j���e�[�v���� |
|
���~�� |
�u���� |
|
|
|
|
�� |
|
|
�@�@�Q�@�����R�O�������炢�������r�j���p�C�v�� |
|
�����A�u�ڂ�ڂ�v |
|
�Q�@�ю��̃Z�[�^�� |
|
|
|
|
�d�C |
|
|
�@�@�@�@�p�����A�e�B�b�V���y�[�p�ł悭�ѓd |
|
|
�@�@����������l |
|
|
�Q�@���~�������������� |
|
|
|
�@�@�@�@�����A�P�@�̂ڂ�ڂ�����Â��� |
|
|
�@�@���w�����A���~ |
|
|
|
|
�Q�@�d�C���������ׂ� |
|
|
|
|
|
�@�@�Ȃǂł悭������ |
|
���� |
|
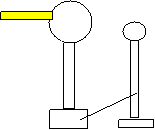
|
|
|
|
|
|
�����r�j���p�C�v |
|
�@�@�Z�[�^���ѓd |
|
|
���C���A���~����������ƁA�������������������� |
|
�� |
|
|
�@(1)�@�X�g���[�ƃV�[�g�����C���āA�X�g���[�ƃV�[�g���d�C���N���� |
|
|
|
|
�@�@������B |
|
���A�X�`���[������ |
|
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
���_ |
|
|
|
|
|
�X�g���[�ƃV�[�g |
|
�@ |
�@ |
�e�B�b�V�� |
�{���{�� |
|
|
�R�@�ѓd�����Ƃ���ŁA�u���������� |
|
|
���������A�{���A���~�����|�����ѓd�� |
|
|
|
|
�����C����B |
|
|
�@�{���{�����e�B�b�V����
�@������ |
+�ɑѓd |
�[���ѓd |
|
|
|
|
�������������� |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�A�����r�j���p�C�v���e�B�b�V���ł����� |
+�ɑѓd |
�|�ɑѓd |
|
|
�@ |
�@ |
�u���� |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
|
�Z�[�^�[�������l���w�� |
|
|
�@ |
�@ |
|
|
�@(2)�@���C�����X�g���[�ƃV�[�g�������������ׂ� |
|
|
|
|
|
|
|
��������A�{���d�C������ |
�u��������u�A�P�� |
�Z�[�^�[�ɂ́A�{�� |
|
�Ód���d���������u |
|
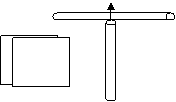
|
|
|
|
|
|
�����A�u�������G��� |
�i�d�C�������j |
�d�C���ѓd���� |
|
|
�X�g���[�ƃV�[�g |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
|
���� |
|
|
|
�������� |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�u�������Ód���d���������u�����Â���� |
|
|
�U�@���������ƂɁu�܂Ƃ߁v�A�u�l���v�悤�B |
�@ |
|
|
|
|
�u�������P�� |
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
|
|
�@�@(1)�@�ѓd�������{���{���������������邱�Ƃ��ł��܂������A�������I�сA |
�܂Ƃ� |
|
|
���_ |
|
|
|
�@�@�@�L���������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
�d�C����������� |
|
|
���C�ɂ��A�d�C���������� |
|
|
|
|
��@�ł��� |
��@�ł��Ȃ����� |
��@���Ȃ����� |
|
|
�d�C�ɂ́A�i�@�@�@�j���Ɓi�@�@�@�j��������B |
|
|
|
|
�ڐG�����Ȃ��Ƃ��A�u�������P�� |
|
�@(3)�@���C�����Q�{�̃X�g���[�������������ׂ� |
|
|
�@�@(2)�@�����ł́A�ѓd�������{���{���������r�j�[���p�C�v���������Ă��� |
|
|
�i�@�@�@�@�@�@�@�j�ǂ����ł́i�@�@�@�@�@�j����B |
|
|
|
|
|
|
|
�@�@���B�������i���������j���������p���������Ȃ��� |
|
|
�i�@�@�@�@�@�@�@�j�ǂ����ł́i�@�@�@�@�@�j����B |
|
|
|
|
|
���C�����Q�{�̃X�g���[������ |
|
���������d�C�����������B |
|
�i�@�@�@�@�j�d�C |
|
|
|
|
|
�������ׂ� |
|
|
�����^���������������@�������������� |
|
|
�Q��������������C���邱�Ƃɂ�����������d�C |
|
|
|
|
|
|
�@�@(1)�@�{���{�������������߁A�����r�j�����A�{���{�����\�����ѓd�������B |
|
|
|
|
|
|
|
�@�@�@�@�������A�{���{���������܂���ł����B���Ȃ����������A�l������ |
|
|
|
|
|
�@�@�@�@���R�������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
�{���{�����d������Ȃ� |
|
|
|
|
���� |
|
|
���x������ |
|
|
|
|
�@ |
���C�����X�g���[�i�P�{�j |
�@ |
�@-�@�̓d�C��ѓd |
�@ |
|
|
|
|
�V�[�g |
�@�@�������� |
�@ |
�@ |
�V�[�g�́@�{�@���d�C���������� |
|
|
|
|
�X�g���[�i�P�{�j |
�@�@�������� |
�@ |
�@ |
�X�g���[�́@�|�@���m������ |
|
|
|
|
|
|
|
| �T�@���������ƂɁu�܂Ƃ߁v�A�u�l���v�悤�B |
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
�i�P�j�@�X�g���[���g���������ŁA�X�g���[�������������A�܂��́A����������������m�F�ł��܂������B |
|
|
|
|
|
|
��@�ł����B |
��@�ł��Ȃ������B |
��@���Ȃ����� |
|
|
|
|
|
�i�Q�j�@�X�g���[���������ł����������������ł����A�����ƂȂ������������Ȃ����B |
�Ód�C�������� |
|
|
|
|
|
|
�@�@�@�܂��A�����������邱�Ƃ��u���v�Ƃ������Ƃ��g�����������Ȃ����B |
|
�u�{���v�Ɓu�|���v�Ƃ����������� |
|
|
|
|
|
�����^���������������@���������������B |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@�����ȊO���Ód�C���������������@���������Ód�C���������m�F�������@�͂Ȃ����낤���A�������@�������Ȃ����B |
|
|
|
|
�h�A�m�u���Ód�C����������B�Z�C�^�[���E�������Ód�C����������B���~��������������B�e���r��������G���B |
|
|
|
|
�l�I�������_�� |
|
|
|
|
| D7102 |
�e�[�} |
��H��������d�����͂��� |
|
|
D7102 |
|
|
|
|
| �S�����T�� |
���� |
���d�r�A���d���i�P�D�T�u�p�j�A�����d���v�A�X�C�b�`�A���� |
�����@�F�@���k����H�������邩�B�d���v�́{�����d�r�́{���ɂȂ����Ă��邩�B�d���v�́[�����[�q���K�����B |
|
|
|
|
���@ |
|
|
|
|
|
|
|
�P�@���d�������������d���@I�@�P�@���͂��� |
|
|
|
|
|
|
���d�� |
|
���d�� |
|
|
|
|
|
�Q�@���d�����������o���d���@I�@2�@���͂��� |
|
|
|
|
|
|
�d���v�@�@�@�@�� |
�d���v |
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
�@ |
I�@1 |
I�@�Q |
|
|
�� |
|
�� |
|
|
|
|
�d���������� |
220 |
220 |
|
|
�X�C�b�` |
|
�X�C�b�` |
|
|
|
|
��A |
mA |
mA |
|
�d�r |
|
�d�r |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 1
= I
2 |
���d���������d�����o���d���Ƃ��������B |

|

|
|

|

|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
|
|
| ���� |
|
|
|
|
|
�d�C���g�����L�����m�낤�B�i�d�r�A���d���A�d���v�A�X�C�b�`�j |
|
|
|
|
|
�d���v���ڑ����d�����P�����m�낤�B |
|
|
|
|
|
|
�ڑ� |
�d���v����H�������������B�܂��A������d�������������킩��Ȃ��ꍇ�́A�ő����[�q�ɂȂ��B |
|
|
|
|
|
�i�TA,�T�O�O��A,�T�O��A)���ꍇ�A�TA���[�q���ڑ�����B |
|
|
|
|
|
|
�P�� |
A�@�i�A���y�A�j�@�@�@�P�@A�@�@���@�P�O�O�O�@��A |
�i�P�@�A���y�A�́A�P�O�O�O�@�~���A���y�A�j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���_ |
|
|
|
|
|
|
���d�������������d���@I1�@�Ɓ@���d�����������d���@I2�@�Ƃ́A�������l�ł������B |
|
|
|
|
|
|
�h�P�@���@�h�Q |
|
|
|
|
|
|
�|�C���g�@�F�@�d�C�����������d���v����������B |
|
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�d���v�́A�������d�C�����������E���ł��A��������p���A�������Ă���B |
|
|
|
|
|
|
|
| �V�@���������ƂɁA�u�܂Ƃ߁v�u�l���v�悤 |
|
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@��H��������d���@I1�@�A�@I2�@���������邱�Ƃ��ł��܂������B |
|
|
|
|
|
��@�ł��� |
��@�ł��Ȃ������B |
��@���Ȃ������B |
|
|
|
|
|
|
�i�Q�j�@���������@I�P�@���@I2�@���W����A���d����������d���ɂ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������܂����A�u���d���v�A�u�d���v�Ƃ������Ƃ��g���������Ȃ����B |
���d����������d�������d�������o���d���Ƃ������� |
|
|
|
�i�R�j�@�R���������ł́A�d���@I1�@���A230��A�@�ł����B���d���������d���@I2�@�́A����A���\�z���܂����B�\�z�l�������Ȃ����B |
�Q�R�O��A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)�@�d���v�ł������₻���ڑ��ɂ��������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
|
��@�d���������������Ƃ����P�����������܂����A�L�����������������Ȃ����B |
A |
�A���y�A |
|
|
|
|
|
��@�Q�R�O��A�́A��A�ł����A�����Ȃ����B |
|
�O�D�Q�RA |
|
|
|
|
|
|
��@�d��������́A�i�@�@�@�j������A�i�@�@�@�j����������������Ă���B�i�@�@�j���K�����L���������Ȃ����B |
�{�@�A�| |
|
|
|
|
|
��@�d���v���ڑ��́A��H�ɂǂ̂悤���ڑ����܂����A�u�����v�u�����v�̂��Ƃ������Ȃ����B |
���� |
|
|
|
|
�����^���������������@�������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
�i�P�j�@���d�����Q�������ɂȂ����ꍇ���d���͂ǂ����낤���A�d��������������H�}�������Ȃ����B |
�ȗ� |
|
|
|
|
�i�Q�j�@���d�����Q�������ɂȂ����ꍇ���d���͂ǂ����낤���A�d��������������H�}�������Ȃ����B |
�ȗ� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D7103 |
�e�[�} |
������H��������d�����͂��� |
|
D7103 |
|
|
|
| �S�����T�� |
���� |
���d���Q���A�����d���v�A���d�r�Q���A�X�C�b�`�A���� |
�����@�F�@���d�����������ڑ�����Ă��邩�B�d���v�́{�|���ڑ������������B |
|
|
|
|
���@ |
|
|
|
|
|
|
�P�@���d��A�����������d��I1 |
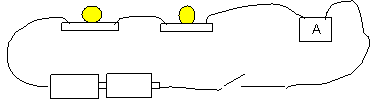
|
���d���@B |
���d���@A |
I�P |
|
|
|
|
|
�@���͂��� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I�Q |
|
|
|
|
|
�Q�@���d��B�����������d�� |
I3 |
|
�d���v |
|
|
|
|
|
�@�@I2�@���͂��� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�R�@���d��B���������o���d���@I3 |
|
|
|
|
|
�@���͂��� |
|
|
���d�r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
�@ I2 |

|
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
I1 |
|
|
|
|
|
�@ |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���� |
�@ |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
|
|
�d���@��A |
�P�P�O�@��A |
�P�P�O�@��A |
�P�P�O�@��A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���_ |
|
|
|
|
|
������H�ł́AI1�@�A�@�h2�@�A�@�h3�@�́A���������Ƃ���A��H��������d�����������͂ǂ��������ł���B |
|
|
|
|
|
|
|
�|�C���g�@�F�@��H��������d�����������������ł��A����ɁA������H��������d���������ł���悤�w������ |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@������H���ł́A�ǂ���������d�����������������������B�i�����i�K�ł́A�d��������Ȃ��j |
|
|
|
|
|
| �W�@���������ƂɁA�u�܂Ƃ߁v�u�l���v�悤 |
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
�i�P�j�@������������A���d���@�`�@�A�a�@��������d���ɂ��Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������܂����A�u������H��������d���v�Ƃ������Ƃ��g���������Ȃ����B |
������H��������d�����������́A�ǂ��������������ł��� |
|
|
|
�i�Q�j�@���d���@�`�@�A���d���@�a�@�����ׂ�ƁA���d���`���������邩�����B |
|
|
|
|
�@�@�@���邳�������̂͂Ȃ����A�������R���������͈��������Ȃ����B |
��R�������������� |
|
|
|
|
���������������Ȃ����B�����́A�L���������Ȃ����B |
|
|
|
|
(1)�@���d��A �����d��B�Ƃ�������������A���邳�͂ǂ��Ȃ邩�ȁA�����������I�сA�L���������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
��@A���ʒu�������@���d��B�@���������邢 |
|
|
|
|
|
��@�ǂ��������ړ����Ă����d��A���������邢�B |
� |
|
|
|
|
|
��@���d���@A
B ���������邳�ɂȂ�B |
|
|
|
|
(2)�@�d���d�����Q�{�ɂ�������d���@A�EB���邳�͂ǂ��Ȃ邩�ȁA�����������I�сA�L���������Ȃ����B |
|
|
|
|
��@�����Ƃ����邭�Ȃ邪�A���d��A���������d��B������邢 |
� |
|
|
|
|
��@���d��B�����邭�Ȃ�A���d��A �EB���������邳�ɂȂ�B |
|
|
|
|
��@���d��A�͂�������邭�Ȃ邪�A���d��B�������Ȃ��B |
|
|
|
|
��@���d��A�EB�����邳�������Ȃ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D7104 |
�e�[�} |
�@������H��������d�����͂��� |
|
D7104 |
|
|
|
| �S�����T�� |
���� |
���d���Q���A�����d���v�A���d�r�A�X�C�b�`�A���� |
|
�����@�F�@������H���d���v���ڑ��ł��Ȃ����k������̂ŁA���w�����K�v |
|
|
|
|
���@ |
|

|

|
|
|
|
|
1 ������H������AI1���ʒu���d������������ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|

|
���d���` |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
�Q�@I2���ʒu���d������������ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
�@ |

|

|
|
�@ |
|
|
|
|
�R�@I3���ʒu���d������������ |
�@ |
|
I3 |

|
I1 |
|
|
|
|
�@ |
���d���a |
|
�@ |
|
|
|
|
�S�@I4���ʒu���d������������B |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
�T�@I1�AI2�AI3�AI4�@���W�����ׂ� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�@ |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
|
|
|
|
|
|
�d���@��A |
�Q�Q�O�@mA |
�P�O�O�@mA |
�P�Q�O�@mA |
�Q�Q�O�@mA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���_ |
������H�ł́A�@�@�h�P�@���@I2�@�{�@�h3�@���@I4�@���W�ɂȂ����B |
|
|
|
|
|
|
������H�ł́A�d���������ꂽ���A�d�����������A��������������������O�������������ł���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�|�C���g�@�F�@��H���ڑ����o���Ȃ����k�ւ��w���Ƃ��āA�������F�������āA�N���b�v���ʒu���}������Ƃ悢�B |
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@������H�ł́A�d��������A�����āA���ꂪ�W�܂�A�����������́A�����Ȃ��B�i���������j |
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@������H��������H����r�w����������ʓI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| �X�@���������ƂɁA�u�܂Ƃ߁v�u�l���v�悤 |
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@������H��������d���ɂ��Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������܂����A�u������H��������d���v�Ƃ������Ƃ��g���������Ȃ����B |
������H��������d�����������́A������邪�d�����������������Ȃ� |
|
|
|
|
�i�Q�j�@���������ŁA���d���`�@�Ɓ@���d���a�@�ƂŁA�d��������ɂ����̂͂ǂ���ł����A�@�`�@�E�@�a�@���L�����g���������Ȃ����B |
A |
|
|
|
|
|
�i�R�j�@���������ɂ��āA���������������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
��@�͂��߂Ă��d���������ŁA�d���v���ڑ��[�q�́i�@�T�`�@�A�@�T�O�O���`�@�A�@�T�O���`�j�̂ǂ���ڑ�����̂��K�����A�R���������I�сA�����������������Ȃ����B |
�TA |
|
|
|
|
��@�����Ắ@�h�Q�@���������������́A�ǂ��ڑ��[�q���ڑ�����̂����������A�����悻�����������킩���āA�������ł������Ƃ��āA�����������������Ȃ����B |
|
�T�O�O��A |
|
|
|
�����^��������������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@���d��B���������d��A������邩�����B���邭�Ȃ����R�������Ȃ����B |
|
���d��B������������d�����������A��R�������� |
|
|
|
|
|
�i�Q�j�@�d���d�����Q�{�����₵���A�d���v�@I1�@��������d���͂ǂ��Ȃ邩�A�����Ȃ����B |
|
�Q�{�ɂȂ� |
|
|
|
|
|
�i�R�j�@�d���d�����P�D�TV�ł������B���d��A�ɂP�O�O��A���d���������ƁA���d��A����R�́A�������A�����Ȃ����B |
�P�T�� |
|
|
|
|
|
�i�S�j�@�d���d�����P�D�TV�ł������B���d��B�ɂP�Q�O��A���d���������ƁA���d��B����R�́A�������A�����Ȃ����B |
�P�Q�D�T�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D7105 |
�e�[�} |
������H�̂��낢���������d�����͂��� |
|
D7105 |
|
|
|
| �S�����T�� |
|
|
�����@�F�@�d���v���ڑ����d�������O���w������ |
|
|
|
|
|
���� |
���d���Q�� |
�d�� |
�d���v |
���� |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |

|
�@ |
|
|
|
|
|
���@ |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
�P�@��H������A�X�C�b�`������� |
|
�@ |

|
|

|
�@ |
|
|
|
|
|
|
�@�d�r�����[���d��E�i�A�E�I�j���͂��� |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|
�Q�@�Q�������d���ɂ������d��E�i�C�E�G�j |
�G |

|
�E�@
�@�@�@�E |

|
�C |
|
|
|
|
|
|
�@���͂��� |
|
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
���d���@B |
|
���d���@A |
�@ |
|
|
|
|
|
|
�R�@���d���ɂ������d��E�i�C�E�E�j���͂��� |
|
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
|
�S�@���d���ɂ������d��E�i�E�E�G�j���͂��� |
�I |
�@ |
�@ |
�A |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|

|
�@ |
|
�u�@�F�@�����d���v |
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�@ |
�u�@��@� |
�u�@��@� |
�u�@��@� |
�u�@��@� |
|
|
|
|
|
|
�d���i�u�j |
3.0 |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���_ |
|
|
|
|
|
|
������H�ɂ����āA�d���������ł́A�@�u���@���@�u���@�{�@V���@���@�u���@���W�ł������B |
|
|
|
|
|
|
������H�ł́A�e�������d�����a���A�d�����d�����������B |
|
|
|
|
|
|
�|�C���g�@�F�@���_������ł��邪�A�d���v������������̂��������ڑ����Ă���̂ŁA�d���v�ɂ��d���������B |
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@���̂��Ƃ��A�d���v���d�g�݂ł����� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �Y�@���������ƂɁA�u�܂Ƃ߁v�u�l���v�悤 |
|
|
|
|
|
���� |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@������H��������d�����������āA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��܂������A�u������H�v�u�d���v�Ƃ������Ƃ��g���������Ȃ����B |
������H��������d�����a�́A�d���d���������� |
|
|
|
|
�i�Q�j�@���d���@�`�@�A�a�@��������d���ɂ��ẮA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������܂������A�ȑO���������v���o���������Ȃ����B |
|
������H�ł́A�d�����������������Ȃ� |
|
|
|
|
�i�R�j�@�i�P�j�Ɓi�Q�j����A���d���@�`�@�E�@�a�@�����������ł����A���������������Ȃ����B |
|
��R�������������� |
|
|
|
|
|
�i�S�j�@�d���v�������ɂ��āA���L�����ŁA�K������̂��������ԍ��������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
�@�@ |
��@�d���v�́A��H�Ɂi�@�@�@�����@�A�@�A�@�����@�j�@���ڑ�����B |
|
�����ɂȂ� |
|
|
|
|
|
|
��@�d�����P���́A�{���g�ŁA�PV�@���@�@�@�@�@��V�@�ł���B |
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
��@����������������d�����킩��Ȃ��Ƃ��́A�i�@�@�@�R�O�OV
,�@�A�@�P�TV�@�A�@�B�@�RV�j���[�q�ɂȂ� |
�R�O�OV |
|
|
|
|
�����^���������������@�������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
|
�i�P�j�@������H�ł��e������d���͂ǂ��Ȃ邾�낤���A���d���Q���g���āA������H��������d��������������H�}�������Ȃ����B |
|
|
|
|
|
�ȗ� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D7106 |
�e�[�} |
������H�̂��낢���������d�����͂��� |
|
|
D7106 |
|
|
|
|
| �S�����T�� |
|
�����@�F�@�ڑ����������₷���̂ŁA�܂�������H�����点�A�����ɁA�����d���v���t��������悤���ڑ�������Ƃ悢 |
|
|
|
���� |
���d���Q���A���d�r�P���A�����d���v |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
���� |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
���@ |
|
�@ |
|

|
|
�@ |
|
|
|
|
|
�P�@������H������A�d���d���u |
�@ |
�u |
|

|
V2 |
|
�@ |
I1 (280mA) |
|
|
|
|
�@�@����������B |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
|

|
I3 (160mA) |
|
�@ |
|
|
|
|
|
�Q�@���d���`���d���u�P������ |
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
�@ |
|
|
|
|
|
�@�@����B |
|
�@ |
�@ |
�@ |
���d���@�a |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
�R�@���d���a���d���u�Q����������B |
|
�@ |
�@ |

|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
|
�@ |
I2 ( 120��A ) |
�@ |
|
|
|
|
|
�S�@���d���`�E�a�ɂ������d���u�R����������B |
�@ |
|

|
|
�@ |
|
|
|
|
|
�@ |
�u�P |
|
�@ |
|
|
|
|
|
���� |
|
�@ |
�@ |

|
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
V3 |
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�u |
�u�P |
�u�Q |
�u�R |
|
�u�@�F�@�����d���v |
|
|
|
�d���i�u�j |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
���_ |
|
|
|
���d���������ɂȂ����ꍇ�A�ǂ����d���ɂ������d����������B |
|
|
|
�u�@���@�u�P�@���@�u�Q�@���@�u�R |
|
|
|
�|�C���g�@�F�@����������H�}������������������������A�Z�����Ă����ƁA�ǂ��������d���ɂȂ邱�Ƃ����������₷���B |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�܂��A��H�}�������Ƃ��ɂ��A�������������ω���������H�}����������������������₷���B |
|
|
|
| �Z�@���������ƂɁA�u�܂Ƃ߁v�u�l���v�悤 |
|
|
|
���� |
|
|
|
�i�P�j�@������H��������d������������A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��܂����A�u������H�v�u�d���v�Ƃ������Ƃ��g���������Ȃ����B |
������H�ł́A�d���������Ȃ� |
|
|
�i�Q�j�@��H�}�����ŁAI1���d��������������Q�W�O��A�AI3���d���͂P�U�OmA�ł����BI2���d����������������A���A�����Ȃ����B |
|
�P�Q�O��A |
|
|
�i�R�j�@���d���@A�@�AB�@����R�����߂Ȃ����B |
|
A�F |
12.5 |
�� |
|
B�F |
9.375 |
�� |
|
|
�i�S�j�@�d���d���@�P�D�T�@V�@�A�@�d���@I1�@�Q�W�OmA �̂Ƃ�����R���������́A���I�[�����A�����Ȃ����B |
|
|
5.357142857 |
�� |
|
|
�����^���������������@�������Ȃ����B |
|
|
|
�i�P�j�@�d�����������������A�d�����d�����W���m�肽���A�d�����d�����W�����ׂ���H�}�������Ȃ����B |
|
|
|
�@�@�@�i�������A�}�ł́A���d�����d�M������������H�}�ɂ��Ȃ����B�j |
|
|
|
�ȗ� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|