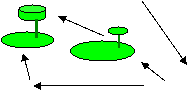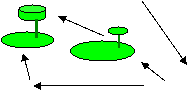|
|
せ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
静電気 |
摩擦によってできる電気を静電気という |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セイタカアワダチソウ |
種子植物 |
双子葉植物 |
合弁科植物 |
キク科 |
帰化植物 |
|
|
|
|
花期 |
9 〜 10月 |
|
|
|
|
特徴 |
まわりの植物より高く成長して日光を多く受け取る。 |
|
|
|
|
|
成長を阻害する物質を分泌する。 |
|
|
|
|
セイタカアワダチソウ(picture) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物 |
生命のあるもの。呼吸をしているもの。動物と植物とを総称して生物という。 |
|
|
|
|
{ 生命 |
呼吸 |
動物 |
植物 } |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セキレイ科 |
セキツイ動物 |
|
鳥類 |
|
スズメ類 |
|
セキレイ科 |
|
|
|
|
地上性で尾が長く、じょうぶな足で歩く。尾を上下にふる性質がある。波上に飛行する。 |
|
|
|
|
細いくちばしで、昆虫などの小動物を食べる。地上の草の間・建物の軒下などに巣を作り、 |
|
|
|
|
雌雄で卵を抱く。繁殖期、非繁殖期を問わない。縄張りをもつ。 |
|
|
|
|
全長 |
13 〜 22 cm |
|
羽色 |
白、黒、灰色、黄、褐色など |
|
|
|
|
つばさ |
初列風切羽9枚 |
|
足 |
足はかなり長く、こうしのつめが非常にのびている |
|
|
|
|
分布 |
世界ほぼ全域に分布し、約50種が知られる。日本では、5種が確認されている |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セグロセキレイ |
セキツイ動物 |
|
鳥類 |
|
スズメ類 |
|
セキレイ科 セキレイ属 |
|
|
|
|
営巣 |
建物の隙間などに営巣する。 |
|
|
|
|
捕食 |
昆虫、エビ、クモ |
|
|
|
|
全長 |
18 〜 22 cm |
|
|
|
|
分布 |
日本特産の鳥で、北海道から九州まで全国的に分布している。川の川原や湖岸に生息。 |
|
|
|
|
特徴 |
ハクセキレイに似ているが、顔の部分が黒い。 |
|
|
|
|
picture(セグロセキレイ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セミ |
不完全変態の昆虫 |
セミ・カメムシのなかま |
セミ科 |
|
|
|
|
|
アブラゼミ |
クマゼミ |
ニイニイゼミ |
ツクツクボウシ |
セミ |
複眼 2 |
単眼 3 |
|
|
|
|
活動時期 |
7〜8月 |
7〜8月 |
7〜9月 |
8〜9月 |
|
成虫は、樹皮のほか、果実からもしるを吸う。枯れ木の他、果実・電柱にも産卵する |
|
|
|
|
鳴き方 |
ジリジリジリ |
シャー・シャー |
ジージー |
ツクツクホーシー |
幼虫は、5〜6年土の中で、木の根から汁を吸って生活する。産卵から、6・7年目ではじめて地上に出る。 |
|
|
|
|
体長 cm |
5.5〜6 |
アブラゼミより大 |
アブラゼミより小 |
アブラゼミより小 |
成虫の期間は、1〜2週間である。 |
|
|
|
|
色 |
茶色 |
透き通った羽 |
茶から灰色 |
透き通った羽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卵 → 胞子のう から 胞子を出す |
|
|
|
ゼニゴケ |
花が咲かない植物 コケ植物 ゼニゴケ |
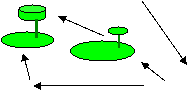
|
受精 |
|
|
|
|
増え方 |
胞子で増える |
|
|
|
|
体のつくり |
維管束(道管、師管など)がない |
精子 |
|
|
|
|
|
根・茎・葉の区別がない |
|
|
|
|
|
|
特徴 |
湿り気の多い所に生活する |
|
雄株 |
|
|
|
|
|
光合成を行う |
|
胞子 |
あるものは雄株に |
|
|
|
|
|
水は体全体の表面から吸収する |
|
あるものは雌株に |
|
|
|
|
|
根は仮根 |
|
|
|
|
picture(ゼニゴケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ゼンマイ |
胞子植物 |
シダ植物 |
ゼンマイ |
|
|
|
|
生育 |
多年生 |
|
|
|
|
背丈 |
0.6 〜 1 m |
|
|
|
|
生育場所 |
低地や山の水辺や林の下 |
|
|
|
|
特徴 |
春早く胞子葉を出し、次に裸葉を出す |
|
|
|
|
|
若い葉は、初め巻いていて、これを採取してゆで、食用にする。 |
|
|
|
|
picture(ゼンマイ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
センリョウ |
種子植物 |
被子植物 |
双子葉植物 |
離弁花類 |
センリョウ科 |
センリョウ(千両) |
|
|
|
|
高さ |
常緑の低木(高さ 50〜60cm) |
|
|
|
|
茎 |
緑色でつやがあり、節が少しふくらんでいる。 |
|
|
|
|
花 |
夏に枝の頂上に短い複穂状花序をつけ2〜3分岐し、柄のない黄緑色の細い花をつける。 |
|
|
|
|
果実 |
花がすむと、小さな球果をつけ、冬に赤く熟す。正月に縁起のよい花として用いられることもある。 |
|
|
|
|
picture(センリョウ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
染色液 |
生物の細胞の観察で、核を染めて見やすくするために使用する染色するための液です。 |
|
|
|
|
よく使われる染色液は、「酢酸カーミン液」「酢酸オルセイン液」です。 |
|
|
|
|
観察では、染色液を1滴プレパラートに落とし、3分ほどしてカバーガラスをかけると、核が染まり、観察しやすいです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生殖 |
生物が新しい個体をつくるはたらきを生殖という。 |
|
|
|
|
生殖には、無性生殖と有性生殖がある。 |
|
|
|
|
無性生殖 |
|
|
|
|
有性生殖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生産者 |
生物界の食物連鎖で、植物が光合成をして、養分を作ることをいいます。 |
|
|
|
|
植物は、太陽の光と水、二酸化炭素から有機物を作り出しています。食物連鎖でこの役割を生産者といいます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|