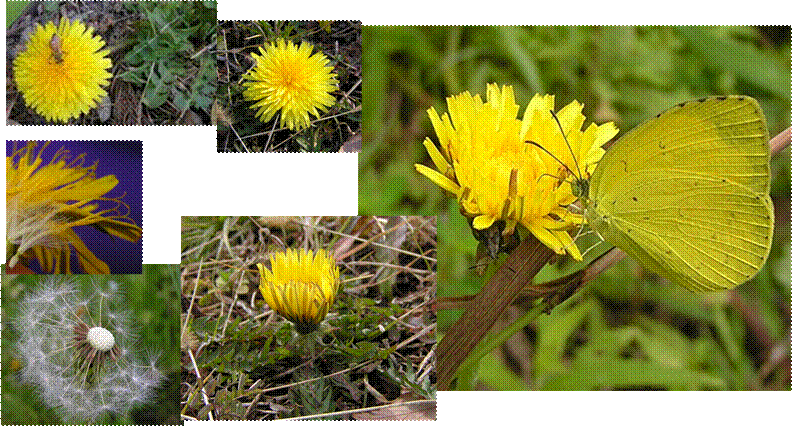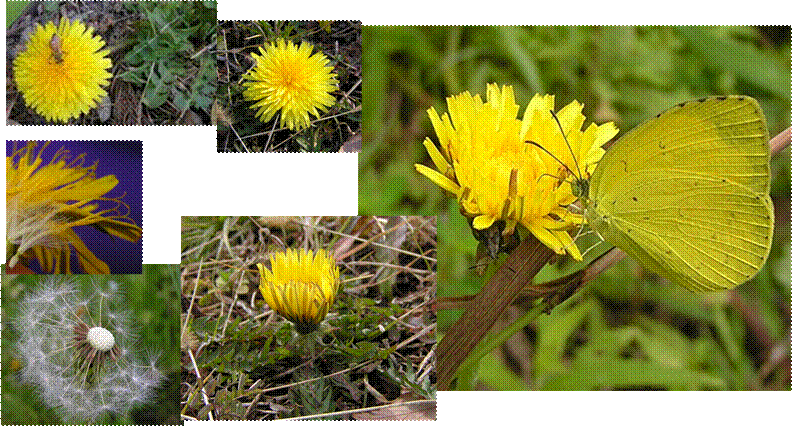| seiyoutannpopo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目次へ戻る |
|
|
|
|
|
|
植物名 |
セイヨウタンポポ |
|
分類 |
|
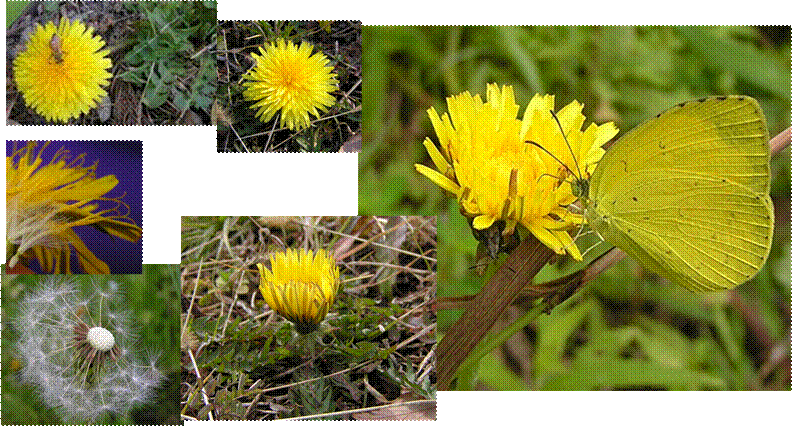
|
|
2006.2.18 |
早朝 9:30 |
|
|
|
|
|
門(もん) |
種子植物 |
|
|
|
|
綱(こう) |
双子葉類 |
|
|
|
|
科・類 |
合弁科類 キク科 |
|
|
|
|
名前 |
セイヨウタンポポ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日 |
2005.4.23 |
2006.2.18 |
2006.2.19 |
|
|
| 2005.4.23 |
早朝(10:00) |
半田緑地 |
|
|
場所 |
浜松市東区半田山 半田緑地 |
|
|
|
|
|
佐鳴湖湖畔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.4.28 種子 |
|
|
特徴 |
佐鳴湖の湖畔に咲くセイヨウタンポポです。 |
|
|
佐鳴湖畔 |
|
|
|
|
黄色の舌状花だけの頭花。直径約4.5cm |
|
|
|
|
|
ハチのいるところは、花の集まりの部分です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セイヨウタンポポは、総包(花の集まりの下の緑色の部分)が |
|
|
|
|
そりかえっています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生育地 |
道・草原・田など、日当たりの良い部分に咲く |
|
|
|
|
|
高さ |
10 〜 25cm |
|
|
分布 |
ヨーロッパ原産の帰化植物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006.7.2 |
半田緑地 |
|
|
|
|
2006.2.19 |
早朝 9:30 |
|
|
|
|
メディア・リテラシー(画像を読み取りましょう) |
|
|
|
|
|
|
|
左上写真 |
セイヨウタンポポの花の集まりにハチが来て、蜜を吸っています。タンポポの花が、数十から百近 |
|
|
|
|
|
(ハチが蜜を吸う) |
く集まって、この大きな花の集まりひとつを作っています。 |
|
|
|
|
|
|
それぞれの花に、おしべ・めじべ・花びら(合弁花)・がく片がついています。そして、それぞれの花 |
|
理数大好き「興味・関心」 |
|
|
には蜜があり、ハチはその蜜をひとつづつ吸っていきます。将来、この花が果実となって運ばれ、子 |
|
○ セイヨウタンポポは花が終ると総苞を閉じ、種子に養分を与え |
|
|
孫を増やします。 |
|
再び開いて、左下写真のようにわずかの風で落下傘のよう |
|
|
花の下、茎をたどっていくと、葉が見えます。この葉は、ギザギザの切れ込みのある葉です。 |
|
に飛びます。その仕組みは巧妙ですがここまで進化するの |
|
|
|
にはどれだけ時間がかかったのかな。 |
|
|
左下2枚写真 |
セイヨウタンポポの花を割ったものと、花が終わり風に飛びつつある種子の集まりです。 |
|
|
○ キク科の植物は花の集まりになっています。花が集まる |
|
|
花の花弁(黄色い部分)がなくなり、種子とがく(白い細い部分)の部分が伸び、果実が成長して |
|
ことで受粉の確立が高くなり、多くの子孫を残すことができ |
|
|
茶色になり、風に乗ってこの果実(中に種子)が飛びます。一つひとつの花がこの種子のように変 |
|
ます。しかし、同じ花の花粉(自家受粉)に近い状態になら |
|
|
化します。がくの部分(細い糸の集まり)は風によく乗り、遠くまで運ばれます。 |
|
|
ならないのかな・・・・・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央上と下 |
2006.2.18・19 写真中央と右上の写真は同じセイヨウタンポポです。時間も同じなのに中央上の |
|
|
|
|
|
|
タンポポは少し閉じています。2.18は晴れて太陽が当たっていましたが、2,19は曇っていました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太陽の光がタンポポンの花の開閉に影響があるようです。また、曇り、気温も低いと昆虫も蜜を |
|
|
|
吸いに来ません。晴れて気温が上がり、確実に受粉がおこなえる状態がつくれた花は子孫を残し |
|
|
|
ます。 |
|
|
|
|
|
|
右の写真 |
セイヨウタンポポの蜜を吸うキチョウです。つぼみが開き始めたところへ最初に来た昆虫がたくさん |
|
|
|
の蜜を吸うことができます。気温が低くとも最初に飛ぶことができた昆虫が食(蜜を吸う)することが |
|
|
|
できる、厳しい自然界に生きるきまりです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|