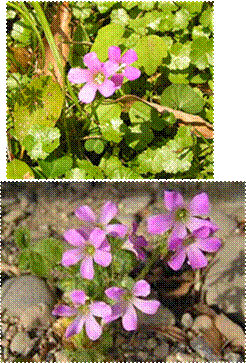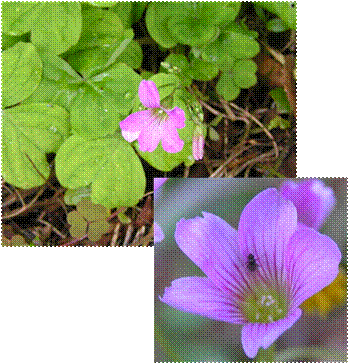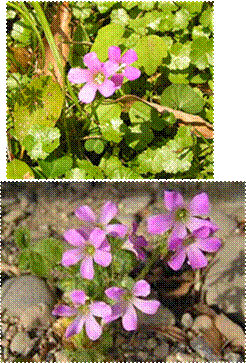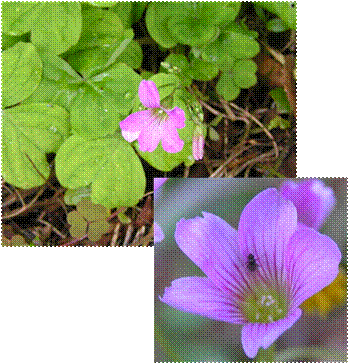| murasakikatabami |
|
|
|
|
|
目次へ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
植物名 |
ムラサキカタバミ(キキョウカタバミ) |
|
分類 |
|
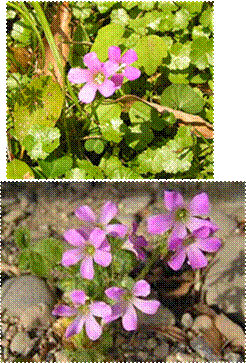
|
|
2005.4.29 |
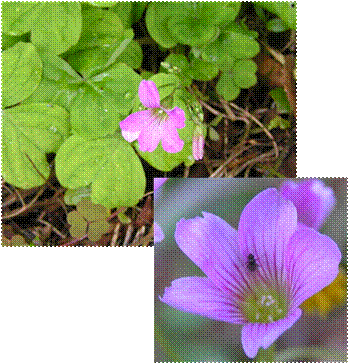
|
|
|
|
|
|
|
半田緑地 |
|
|
|
2006.5.20 |
門(もん) |
種子植物 |
|
|
|
佐鳴台 |
綱(こう) |
双子葉類 |
|
|
|
科・類 |
離弁花類 カタバミ科 |
|
|
名前 |
ムラサキカタバミ |
|
|
|
|
|
|
撮影日 |
2005.4.29 2006.2.4 |
2006.5.20 |
|
|
場所 |
浜松市半田山 半田緑地 |
佐鳴台 |
|
|
|
|
|
|
特徴 |
多年草(地下部が残り翌年花を咲かす) |
|
|
|
葉は小葉3枚で逆さの心臓の形(倒心臓形)です。 |
|
|
|
花は5弁花、おしべ10本、花柱5本です。果実は実 |
|
|
|
りません。地下茎で増えます。 |
|
|
|
|
|
観賞用に栽培されたものが野生化して広がりました。 |
|
|
|
花に紫色のスジがあることからムラサキカタバミの |
|
|
|
名前がつきました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生育地 |
道ばた、庭 |
|
|
|
2008.12.28 |
|
分布 |
関東地方以西 |
|
|
|
半田緑地 |
|
|
南アメリカ原産の帰化植物 |
|
|
2007.5.26 |
佐鳴台 |
|
|
|
|
|
メディア・リテラシー(画像を読み取りましょう) |
|
|
|
|
|
|
左上写真 |
チドメグサなどの中に咲いたムラサキカタバミです。2つの花が太陽の方向に向き, |
|
|
|
|
互いに競うように光をうけています。同じ茎から伸びた花なのに競って子孫を残そうと |
理数大好き「興味・関心」 |
|
|
|
|
|
するのはなぜでしょうか。 |
|
○ ムラサキカタバミとカタバミは同じカタバミ科なのに |
|
|
|
色や大きさが異なります。その似た点と違いは何でし |
|
|
左下写真 |
ムラサキカタバミがまとまって咲いています。おおかた同じ方向を向いて咲いていま |
ょうか。 |
|
|
|
|
す。葉の数に比べて花の数が多いのは,なぜでしょうか。 |
|
○ 右上の写真にはムラサキカタバミの隣にカタバミの |
|
|
|
|
|
葉があります。カタバミ科同士ですが何か関係がある |
|
|
右上写真 |
ムラサキカタバミの花とつぼみ、葉が見えます。手前の小さな葉は、カタバミの葉で |
のでしょうか。 |
|
|
|
|
す。カタバミの葉と比べると葉がずいぶん大きいです。 |
|
○ 12月に花を咲かせるムラサキカタバミは,季節の |
|
|
花の付いた茎が伸びています。途中に葉がありません。 |
|
影響を受けないのでしょうか。また,冬のハエでも受精 |
|
|
|
|
するのでしょうか。 |
|
|
|
|
右下写真 |
ムラサキカタバミの花にハエがいます。12月28日の14:00頃の写真です。冬でも |
|
|
|
|
|
暖かい時間には昆虫が少ない花の蜜を吸いに動き,子孫を残そうとする自然界の厳し |
|
|
|
|
|
|
|
さに耐えて生きるすばらしさと感動の場面です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|