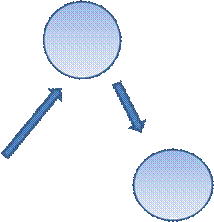| kawasemi |
|
|
|
|
|
|
|
目次へ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
動物名 |
カワセミ |
|
分類 |
|

|
|
|
|
|
|
|
| 2006.12.10 |
|
|
← |
2010.11.14 |
|
門(もん) |
セキツイ動物 |
|
|
| 佐鳴湖 |
|
半田緑地 |
|
2010.11.14 |
半田緑地 |
綱(こう) |
鳥類 |
|
|
|
科・類 |
ブッポウソウのなかま カワセミ科 |
|
|
名前 |
カワセミ |
|
|
|
|
|
|
|
撮影日 |
2005.8.21 2006.12.10 |
|
|
|
場所 |
浜松市半田山 半田緑地 佐鳴湖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特徴 |
背はコバルトブルー色、頭や羽が金属光沢 |
|
|
|
|
|
のある緑色、目の後ろと胸から腹にかけて |
|
|
|
|
|
|
|
オレンジ色をしています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長いくちばしがあります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体長 |
17cm |
|
|
|
|
|
|
|
分布 |
日本全国(平地〜山地) 川・池・湖 |
|
|
|
|
時期 |
夏の写真と冬の写真から、1年中水辺にいます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008.8.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
佐鳴湖畔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メディア・リテラシー(画像を読み取りましょう) |
|
|
ヌマエビを食べるカワセミ |
「カワセミの ねらうヌマエビ 寒助け」 |
理数大好き |
|
|
左上写真 |
佐鳴湖 東岸 浄化用のアシ原の杭(くい)に止まるカワセミです。 |
|
|
実験 2011.07.26 |
○ 左上写真、カワセミの口ばしが頭の大きさに比べて |
|
|
全体にブルーと目の後ろ、胸から腹にかけてオレンジ色が確認できます。 |
|
|
長く、先端が鋭いです。これは水中の動物を捕まえる |
|
|
長い口ばしで、その先には浅瀬に動く魚などをとらえています。この日は、朝9:00頃で気温も低く魚の動きも鈍い |
|
のにつごう(すばやく,つかみやすいなど)がよいです。 |
|
|
ときです。急降下をしては、同じ場所(この杭)に戻っています。 |
|
○ 左下の写真はカワセミの飛ぶところです。両方の羽 |
|
|
|
|
を持ち上げ、羽の先端がぶれています。そこから先端 |
|
|
左下写真 |
カワセミが飛び立つところです。羽の先が小刻みに震えています。身体に比べて小さな羽ですが羽の幅が広いです。 |
|
部分では早い動きが読みとれます。 |
|
|
|
|
○ 中央の写真は流れる湧水の中の動物を狙っていま |
|
|
中央写真 |
半田緑地の溝を流れる湧水(わきみず)の中に動く動物を探(さが)し,その動きを見つけたようです。川下から数m |
|
す。溝の壁に足の爪をかけ素早く飛び込む体勢にな |
|
|
づつ上流に移動して魚などの獲(え)もののすきを狙います。 |
|
っています。脚力と重力で獲物に飛びかかります。 |
|
|
○ カワセミがヌマエビを捕(つか)まえました。水温が低く |
|
|
右写真 |
カワセミがヌマエビを捕まえました。口ばしとヌマエビが垂直になっています。水中に飛び込み反転してエビをくわえて |
|
一瞬のすきにつかまったようです。ヌマエビは尾のほうか |
|
|
もとの場所に戻ってきました。トゲの多い頭を後にエビの尻尾(しっぽ)から飲み込みました。 |
|
ら飲み込まれます。 |
|
|
|
|
この日の状況 (11/14 晴れ 午後16:00頃 撮影) |
|
|
|
|
ヌマエビのいるわき水も流れることで水温が下がっています。 |
|
|
浜松理科教育研究会 「科学の楽しさ・素晴らしさ」 講演会から 抜粋 |
|
変温動物と恒温動物 |
|
|
|
|
「温度と生物の動きを生命と素粒子の関係」で、 |
|
|
|
素粒子 : 6種類のクオーク |
※ フェルミ統計 レプトンとクォークから6種のクォーク |
|
どのように説明できるのでしょうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カワセミ |
ヌマエビ |
|
|
|
|
原子 |
|
陽子 |
|
同じ点 |
|
|
|
|
|
|
|
生物は進化して環境に適したと言われますが |
|
|
|
|
エビもカワセミも同じ時(時間)に生活しています。 |
|
|
|
0.0000001m |
|
エビやカワセミの身体は有機物で,構成する |
|
|
|
|
分子の種類や数は多少の違いはありますが,身 |
|
|
ウイルス |
|
|
近な原子でできています。また、DNAを構成する |
|
|
10のマイナス7乗 |
×1/100 |
|
×1/10,000 |
|
×1/1000 |

|
|
原子の種類は同じです。 |
|
|
メートル |
|
百分の1 |
|
一万分の1 |
|
千分の1 |
|
身近な原子を構成する素粒子のどれも全てが |
|
|
|
|
ヒモ? |
運動しています。 |
|
|
|
×1/10 |
|
×1/10 |
|
|
|
|
|
|
十分の1 |
|
十分の1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
異なる点 |
セキツイ(カワセミ) |
無セキツイ動物(ヌマエビ) |
|
|
|
|
鳥類 |
節足動物 甲殻類 |
|
|
|
|
恒温動物 |
変温動物 |
|
|
|
分子 |
|
|
原子核 |
|
クォーク(6種類) |
(寒くとも体温が一定) |
(気温が下がると体温も |
|
|
|
|
10のマイナス18乗より |
|
|
下がる) |
|
|
|
|
小さい |
|
|
|
|
|
|
物理法則は物質・反物質の対称性をわずかにやぶっている。このやぶれによって長い時間(137億年)をかけて物質だけになった。 |
気温が下がり、ヌマエビの運動の速さが遅くなった。 |
|
|
|
講師 「静岡文化芸術大学 有馬朗人 理事長」から 2010.11.14 |
|
気温が下がってもカワセミの運動の速さは変わらない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ フェルミ統計は粒子のスピン角運動量が整数の半分とする量子力学で説明されている。 |
|
|
「低い体温の中の素粒子全体の運動は、高 |
|
|
考察 |
|
|
い体温の中の素粒子全体の運動よりわずか |
|
|
|
クオーク、陽子、中性子、原子、電子、分子の全てが運動している状態にあって、温度の高い細胞と低い細胞とでは |
に遅い」とすると、ヌマエビが捕(つか)まった |
|
|
その含まれる全ての物質の運動に速さに違いが生じる。温度が低いと速さが遅い。 |
|
理由になります。 |
|
|
このことから、変温動物は、気温が下がると動く速さが遅くなる。 |
|
俳句で説明 |
|
|
|
|
参考に |
|
「カワセミの ねらうヌマエビ 寒(かん)助(たす)け」 |
|
|
「ヒモ」も高速スピンする。高速スピン同士は手をつなぐことが可能です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(平行に走っている新幹線同士は手をつなぐことが可能です。また、宇宙船のドッキングで説明される) |
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに |
6つのクオークが2づつ手をつなぎ3つの粒子となって存在すると、その3つの結びつきはオゾン(O3)の結びつきと同 |
|
|
|
じような結びつきがイメージできます。オゾンは分子量が酸素(O2)より大きいのに上空にオゾン層をつくります。 |
|
|
|
|
酸素が発生し、植物をつくり、植物は重力に逆らって上に伸びていきます。このこの講演会はひじょうに多くのイメージ |
|
|
|
の膨らむ講演会でした。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|