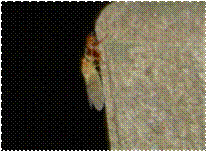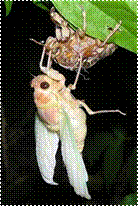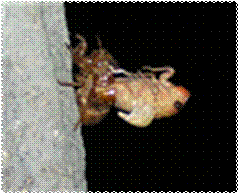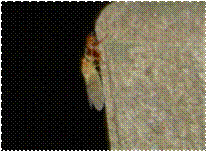| aburazemi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目次へ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
動物名 |

|
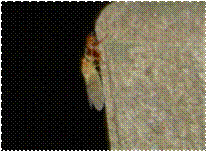
|
|
分類 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
門(もん) |
無セキツイ動物 節足動物 |
|
|
|
|
|
綱(こう) |
昆虫類 |
|
|
|
|
|
|
|
科・類 |
カメムシ目 セミ科 |
|
|
|
名前 |
アブラゼミ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撮影日 |
2004.7.24 2006.8.22 |
2007.8.6 |
2008.8.21 |
|
|
場所 |
浜松市東区半田山 半田緑地 |
|
|
|
2006.8.22 |
半田緑地 |
|
他の観察場所 |
佐鳴湖畔 |
東京都板橋区光が丘公園 |
|
|
|
|
落ちるぎりぎりのところの羽化(重力と支える力) |
|
|
|
|
|
特徴 |
夏、日本のいたる所で、油の煮えたぎるようなやかまし |
|
|
い声で鳴きます。 |
|
|
|
|
口は注射針のような形で、植物の汁や昆虫の汁を吸っ |
|
|
ています。 |
|
|
|
卵 |
枯れた幹や枝、木の電柱に2,3個ずつ産みます。 |
|
|
1齢幼虫 |
卵は越年し、翌年7〜8月に第1齢幼虫となり、地下にも |
|
|
ぐります。 |
|
|
|
幼虫 |
地下で樹根より吸汁して成長し、7年目の夏に地上に現 |
|
|
れ、最後の変態をして、成虫となります。 |
|
|
体長 |
50 〜 60 mm |
|
|
|
分布 |
北海道、本州、四国、九州 |
|
|
| 2008.8.21 |
東京都板橋区光が丘公園 |
2007.8.6 |
21:00 |
半田緑地 |
|
2009.8.5 |
半田緑地 |
|
|
|
|
メディア・リテラシー(画像から読み取りましょう) |
|
|
左上写真 |
このアブラゼミと左のアブラゼミを比べると色が濃く、体や羽が堅く固まって |
|
|
|
|
います。卵が幼虫になり、地下で7〜8年過ごし、地上に出て、羽化し、体が |
|
理数大好き「興味・関心」 |
|
|
|
|
|
|
固まり、交尾して一生を終えます。生まれ成長したものはもとに戻らないです。 |
|
○ 土の中の幼虫、羽化した成虫、土の中と地上 |
|
|
|
|
樹液を吸うアブラゼミです。6本の足の先のカギのような部分を使い木の幹 |
|
とは環境の違いはどれだけだろうか。 |
|
|
|
をつかみ、体を固定しています。木の幹には昆虫が止まりやすいよう凹凸が |
|
○ 地上から地下にもぐり、再び地上に出て交尾し |
|
|
|
あります。樹木と昆虫が共生しています。 |
|
卵を産む。樹木と蝉の関係はどれほどだろうか。 |
|
|
|
|
○ セミの羽化では、殻から体を出す場合、落ちる |
|
|
|
左写真 |
アブラゼミの交尾です。上からこの状態で落ちてきました。この状態では |
|
寸前まで体をのけぞります。落ちないのが不思議 |
|
|
トンボのように飛べません。しばらく後、それぞれが幹に向かって飛び立ちました。 |
|
です。羽化と地球の重力は関係があるのでしょうか。 |
|
|
|
|
か。 |
|
|
|
|
|
|
中央上右写真 |
林の中、神社の囲いの石上で羽化を終えたアブラゼミです。 |
|
|
|
|
|
中央写真 |
身体がうすい緑色からアブラゼミの特徴の茶色い色に変化してきています。 |
|
|
|
|
|
羽化が成功し、羽の固まるのを待っているところです。 |
|
|
殻の6本の足は、脱皮中、脱皮後もその体重を支えています。 |
|
|
|
夜明けには、飛び立ちます。 |
|
|
|
アブラゼミの羽化です。2枚の内の右下から左上の状態に時間とともに変化 |
|
|
します。この右下では、落ちるぎりぎりの状態まで体を殻から出しています。 |
|
|
まるで、これから飛び出す世界の重力を測定しているようです。 |
|
|
|
その左では、翅が伸び始めました。夜のうちに羽化を終え、朝から飛び回 |
|
|
り受精を行い、子孫を残します。 |
|
|
|
|
|
|
|
右下写真 |
羽化の終わったアブラゼミです。夕刻6:00頃,この時間の羽化は珍しい。 |
|
|
|
(深夜に羽化をし,早朝飛び立つ場合が多い) |
|
|
羽化が成功し,ちじんでだ白い羽に,緑色の筋(すじ)が見えます。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|