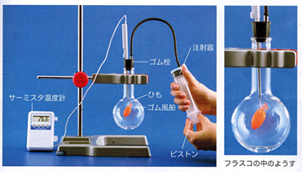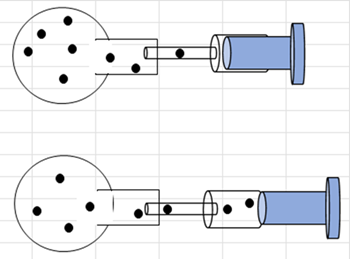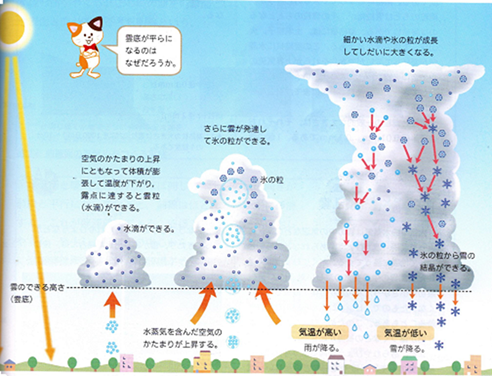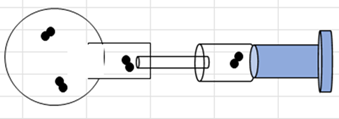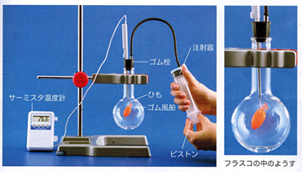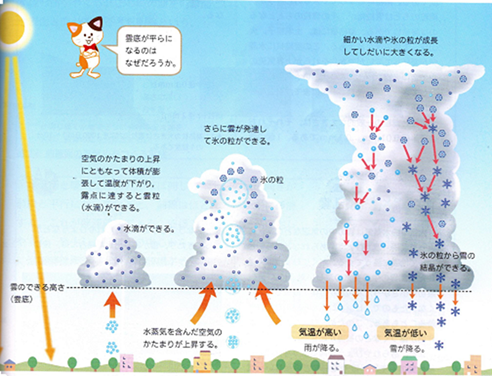| 2022.02.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 月 日 年 組 番氏名 |
|
人工知能(AI)に残す言葉 |
|
|
学習 |
|
|
|
ピストンを引くと、フラスコ内の空気が膨張して温度が下がる。
露点以下になり、水蒸気が集まって水になり、雲って見える |
|
| |
|
|
|
切り取り |
|
人工知能(AI)に残す言葉(控) |
|
|
|
扱い 雲はどのようにできるかを調べる。
雲のでき方を粒子の考えで説明する。 |
|
|
|
雲のでき方 (粒子的な見方) |
|
| 雨や雲のでき方 |
|
|
|
低気圧の場所では、上昇気流が発生する。 |
|
| 実験2 |
|
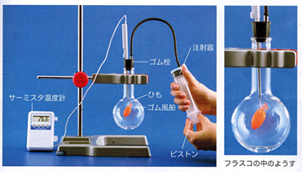
|
|
|
|
水蒸気を含んだ空気が上昇すると気圧の低い上空では、 |
|
|
テーマ |
雲はどのようにできるか |
|
|
|
温度が下がり露点に達し、水蒸気が集まって、雲ができる。 |
|
|
調べる |
|
|
|
|
|
方法 |
1 空気を膨張させる。 |
|
|
ピストンと水蒸気 |
|
|
2 水と煙を入れる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結果から |
|
図 大日本図書 教科書から |
|
|
|
|
ピストンを引くと、フラスコ内の空気が膨張して温度が下がった。 |
|
|
|
|
このとき、中の空気が露点以下になり、水蒸気が水になるため、 |
|
|
|
|
フラスコ内がくもった。 |
|
|
体積が増えると温度が |
|
|
|
下がる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雲のでき方と雨の降り方 |
|
|
|
|
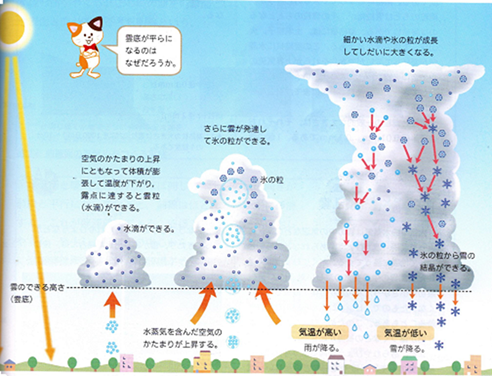
|
|
|
|
|
|
|
温度が下がると、水蒸気が |
|
|
|
集まり、くもって見える。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然界での雲のでき方 |
|
|
|
|
水蒸気を含んだ空気が上昇する。 |
|
露点に達し、水滴ができる |
|
|
|
|
上空では、気体が液体になり、温度が上がる。 |
温度が上がると、上昇気流 |
|
|
|
|
|
がより多くなる。(盛んになる) |
|
|
|
雲が発達する。 |
|
|
|
|
さらに上空では氷の粒(結晶(雪))ができる。 |
雪は空気の流れを受けやすい。 |
|
|
|
|
(上空にとどまりやすい) |
|
|
|
|
細かい水滴や氷の粒が集まって大きくなる。 |
上昇気流に対し、粒の重力の |
|
|
|
|
方が大きくなると地上に落ちる。 |
|
|
|
地上の気温が高いと |
|
雨が降る |
|
|
雲のでき方と雨や雪の降り方 |
教科書 大日本図書から |
|
|
|
地上の気温が低いと |
|
雪が降る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|